所属部署 経済グループ
氏名:石川淑子
ジニ係数とは、イタリアの統計学者コンラッド・ジニが1936年に考案した指数で、所得格差を表す代表的な指標です。横軸に世帯数の累積比、縦軸に所得額の累積比をとり、世帯を所得の低い順に並べた際に所得額の累積比が描くローレンツ曲線と均等分布線で囲まれた部分(a)の面積が、均等分布線より下の三角形(b)の面積に占める割合を指します(図1)。所得が完全に平等に分配されている時には(a)の面積が0となり、逆に一世帯が所得を独占している時には(a)と(b)が一致するため1となります。つまり、ジニ係数は0と1の間の値をとり、1に近いほど所得格差が大きいことを示します。
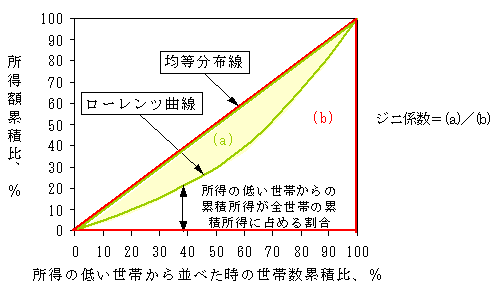
しかし、ジニ係数は所得格差の「固定化」を表す指標ではないことに留意しておくことが大切です。例えば、2世帯しか存在しない世界で、昨年の所得が世帯Aで100万円・世帯Bで900万円であり、今年の所得が(1)世帯Aで100万円・世帯Bで900万円となった場合と(2)世帯Aで900万円・世帯Bで100万円となった場合について見ると、ジニ係数は昨年、今年(1)、今年(2)のいずれも0.4と、同程度の所得格差の存在を示します。ところが実際には、(1)では格差が固定化しているのに対して、(2)では順位の入れ替えが生じた結果、昨年、今年の2年間をならしてみると格差が解消しており、(1)と(2)では状況が異なります。ジニ係数を利用の際は、こうした可能性を念頭に置いておくことが必要です。
2007年8月に厚生労働省が公表した「平成17年所得再分配調査」によれば、日本のジニ係数は当初所得で0.5263と、上昇傾向をたどっています。一方、当初所得から税や社会保険料を引き、社会保障給付を加えた再分配所得は0.3873となっており、税や社会福祉などにより不平等度が緩和されていることが分かります。もっとも、再分配所得のジニ係数も、当初所得ベースと比べれば上昇ペースは緩やかながら上昇傾向にあり、所得の再分配が行われたベースでも所得格差は広がっています(図2)。
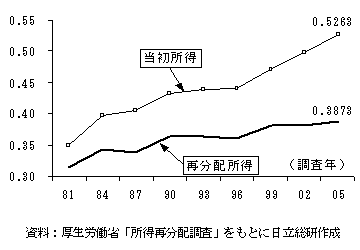
(図2)ジニ係数の推移
ジニ係数が近年注目される理由としては、これまで先進国の中で比較的平等といわれていたわが国も、米国のような格差社会になりつつあるとする意見が、メディアなどで取り上げられていることが挙げられます。実際、わが国の状況をみると、マクロ全体では景気回復が続いてきましたが、それは大企業が中心であり、中小企業では景況感の回復に乏しいところが少なくありません。また、正社員と比べ、非正規雇用であるパートやフリーターには景気回復の恩恵が行き届かず、働く貧困層といわれるワーキングプアの問題も生じています。さらに、地域的な状況をみると、大都市圏は回復傾向が明確化する一方で、地方ではいわゆるシャッター通りにみられるように、厳しい状況が続いています。
こうした中、福田首相は2007年10月1日の所信表明演説の中で、格差是正に言及しており、今後の政策対応は、構造改革による競争促進的なものから、弱者にある程度配慮した、安全・安心重視型に切り替わる可能性が出てきています。「機会の平等」を確保するためには教育や職業訓練などの施策が重要ですが、どの程度の「結果の平等」を達成すべきかは、今後国民の合意形成によって決められていくこととなるでしょう。
機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。
お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。