所属部署 研究第一部
氏名:高橋孝*1
AOGCM(Atmosphere-Ocean General Circulation Model)とは、IPCC第4次報告書において気候予測の中心になっている気候シミュレーションモデルの総称で、「全球大気海洋結合大循環モデル」などと訳されます。
IPCC報告書のメッセージが広く知られていることに比べ、その根拠になっている気候予測モデルなどの技術的な情報はあまり一般的になっていません。そこで以下では、AOGCMをはじめ気候予測モデルの具体的なイメージについて簡潔に整理してみたいと思います。
IPCCでは23のAOGCMを採用 IPCCの第4次報告書では、海洋の作用*2やCO2の効果をはじめ、他のさまざまな物理過程を取り込み、かつ一定の精度が検証されたモデルとして、以下の23のAOGCMが採用されています(日本からは2機関、3つのモデル)。これらはいずれも、広義には「全球プリミティブ・モデル」といわれるタイプに分類されます。

(資料)IPCC AR4(2007)Chapter8(機関名は大西晴夫元気象庁地球環境・海洋部長の講演資料を参考にした)
Tは水平解像度を示し、解像度=360°/(3T+1)という関係がある(中緯度では1°≒111km)。Lは鉛直方向の層数
まず「プリミティブ」という言葉の意味ですが、これは一般的なイメージである「原始的な」「初歩的な」というニュアンスとは少し異なります。むしろその逆で、「基本的な原理までも(省略せずに)計算に取り込んでいる」というポジティブな意味をもっています。その具体的なイメージは以下のようなものです*3。 最初に、数値計算を行うための座標を地球上に定めます。これは基本的に緯度・経度をベースに数百kmオーダーの間隔で設定され、さらに、それを鉛直方向に数十層重ねて地球大気を立体格子状に網羅します。海洋についても基本的には同様に格子状の座標を設けます(具体的な解像度については前出の表をご参照ください)。これらの格子点に気象変量(例えば気温なら気温;総称してGrid Point Value:GPVと呼ばれます)を与え、物理過程を表現した方程式に従って将来の推移をシミュレーションしていきます。これには大きく分けて以下の2つの方法があります。
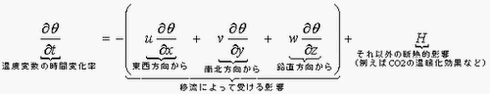
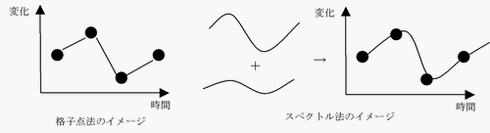
前出の表の各モデルの解像度によれば、大気部分でおおむね200〜300km程度です。一般に、モデルによって表現できる気象現象の最小スケールは格子間隔の5倍程度なので、AOGCMによる予測は、日本でいえば「東日本の気候」「西日本の気候」といった程度の大まかな見積りに相当します。このような気象現象の規模を「総観スケール」といいます。
計算の開始にあたって各格子点上に与える初期値は、地上観測や衛星観測によって得られた観測値を一定期間平均化したものなどを用います。そして時間ステップに応じてシミュレーション計算を行っていきます。この時間ステップは、数十年先の予測の場合であっても大気モデルで1ステップ数十分程度、海洋モデルで1ステップ数時間程度です。もちろん、モデルによって違いがあり、一般に格子が細かいほど時間ステップも短くするという原理があります*5。
数十分、数時間という短いステップで、数十年分という期間にわたって、地球上の膨大な数の格子点について計算を行っていくわけですから、高性能のスーパーコンピュータが必要とされる理由も納得できます。ちなみに、日本の「地球シミュレーター」クラスのスーパーコンピュータでも、1回の計算に月単位の時間を要しています。
IPCCでは複数の計算結果を総合して将来の気候値を見積っています。多数の計算結果から平均的な振舞いを見極めることをアンサンブル手法と呼びます。各モデルとも非線形性による初期値依存性(いわゆるカオス現象)をもつため、一つのモデルの中で何通りもの計算を行って計算の安定性を確かめます。さらに、各モデル同士で平均がとられる場合もあります。IPCCではこの両者を合わせてアンサンブルという表現を用いています。
IPCC報告書では、将来の気候値について、予測の幅を示した確率的な表現が多用されていますが、それは各予測アンサンブルによるばらつきの程度に基づいています。
IPCCは、第4次報告書で採用されたモデルについて、「大陸規模の気候予測といったレベルではかなりの信頼性がある」と高く評価していますが、この成果には日本の研究も多大な貢献をしています。 日本で数値気象予測(ここでは気候予測でなく短期の数値予測)が開始されたのは1959年、気象庁に初めてスーパーコンピュータが導入されたことに端を発します。これは米国(1955年に数値予報業務化)に次いで世界で2番目ですが、当時の数値予測は精度が悪く、なかなか気象実務に活用されない状態が続いたといいます。
しかし1970年代以降、衛星観測網の整備などによって数値予測の精度は飛躍的に向上し、また日本の場合、特に台風進路予測の必要性などから、数値予測の技術は世界的水準に高まります。さらに近年の計算機性能の向上によって格子スケールの詳細化や全球モデルの日常的活用が進み、現在ではモデル計算の結果によって逆に観測機器の不具合を発見することがあるという水準にまで精度が向上しているそうです。
短期の数値予測と長期の予測については性質が異なりますが、長期の気候モデルについても日本の研究レベルは世界水準にあります。モデル構築をリードしているのは米国であるという構図はあるようですが、日本は国土が狭く地形が複雑であることから、きめ細かい気象予測の必要性が高く、高解像度のモデル構築が進んでいます。前出の表の日本のモデル(No.18)はIPCCに採用されたモデルの中でも際立って解像度が高く、特に海洋の中規模渦の表現が可能なのは世界でこのモデル(MIROC)だけであるとの評価もあるほどで、この分野では国際的な優位性を保持しているといえます。高性能のスーパーコンピュータへのアクセスに恵まれていることも日本の利点です。
現在のAOGCMには、IPCC自身も指摘しているとおり、雲(特に下層雲)の取り扱いをはじめさまざまな課題があり、多くのモデル作成者もAOGCMの不完全性を認識しています。しかし同時に、将来の気候を考えるにあたって、AOGCMが最も重要な道具であるというのも関係者の一致した意見です。今後、モデル進化への期待はますます高まることでしょう。
機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。
お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。