所属部署 エネルギー・環境グループ
氏名:蜷川典泰
地球温暖化問題は、従来の環境問題と比べると、その対応策は大きく異なります。温暖化の原因である温室効果ガスの排出規制などが効果を生むまでには、何十年単位の時間がかかります。逆に言うと、既に過去に排出した温暖化ガスの影響で地球の平均気温は0.7℃上昇してしまっていますし、今後数十年にわたり更に温暖化が進むことは避けられません。地球温暖化問題の核心は、これ以上の温暖化の進展を食い止めるための対策の実施です。
したがって、その主要な対策である温室効果ガスの排出規制などを「緩和策(mitigation)」と呼びます。他方、一定の地球温暖化は避けられない状況ですので、地球人としてはそれに適応することが求められます。すなわち、地球温暖化による影響や被害への対策も必要であり、それを「適応策(adaptation)」と言います。これには、温暖化によって深刻化する自然災害に備えたインフラ強化やその他人間社会への悪影響を軽減するための対策が含まれます。
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が、2007年に発行した第四次評価報告書は、人為起源の温室効果ガスの増加と温暖化の因果関係をほぼ断定しており、地球温暖化対策が喫緊のグローバル課題となっています。これまでは先進国を中心とした対策が中心であったのに対して、現在では発展途上国も参加して、京都議定書の次の枠組みを構築するための努力が続けられています。
これまで地球温暖化対策として取り上げられてきた方法の多くは、地球温暖化の「緩和」を目的とした取り組みでした。たとえば、環境省発表資料によると、「緩和」を目的とする日本政府の京都議定書目標達成計画関係予算(平成20年度)は総額1兆2,166億円を計上しました。さらに先進国を中心とする世界各国は、世界全体で2050年までに温室効果ガス排出量を半減する目標を検討しようとしており、「緩和」に向けた長期ビジョンを次々に打ち出しています。一方、日本政府が地球温暖化「適応」のために計上する予算は1億5,000万円にすぎず、「適応」策に関する国際的な議論も、ようやく本格化し始めたという状況です。
一方で、地球温暖化は着実に進行していることが明らかになってきています。先に述べたように、前述のIPCC報告書は、地球の平均気温が、過去百年間に既に0.7度上昇したと述べています。また、温暖化によって、熱帯低気圧が大型化すると予測されているほか、温帯気候でのマラリア流行、海面上昇に伴う高潮・洪水被害、頻発する干ばつ・熱波が世界各地の人々を危険な状態にさらすと言われています。
さらに、同報告書によると、21世紀末までに地球の平均気温が20世紀末に比べて1.1〜6.4度上昇する可能性があると予測しています。こうした影響のリスクは、アフリカ諸国や太平洋島しょ国など、低緯度地域に属する途上国において大きいとされていますが、日本などの先進国もこのリスクを免れるものではありません。
地球温暖化対策は、「緩和」策にとどまらず、既に進行している地球温暖化の被害を最小限に抑えるための「適応」策の推進が必須だと言えるでしょう。 元世界銀行チーフ・エコノミストのニコラス・スターン博士は、英国政府の依頼を受けてまとめた著名な報告書「気候変動の経済学(The Economics of Climate Change)」の中で、「適応」策の実施に際し、現行の市場経済システムが抱える限界として(1)情報の不確実性・不完全性、(2)堤防・橋など公共財を保護・強化する取り組みの不足、(3)低所得層への被害の集中、の3点を挙げています。スターン博士は、政府の適切な支援により、これらの問題を軽減することができると主張しています。 既に先進国、途上国を問わず、次のような「適応」策に関する先進的な取り組みも確認できます(下表)。
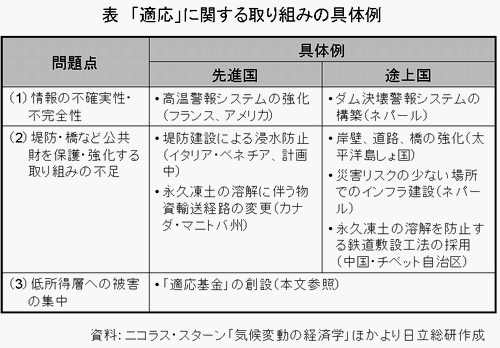
「適応」策の一つである「適応基金」とは、地球温暖化の影響を受けやすい島しょ国や発展途上国に対して資金的支援を行う国際的取り組みです。インドネシアのバリで開催された気候変動枠組条約第13回締約国会議(COP13)で採択された「バリ・ロードマップ」でも、適応基金の運営原則・形態が整うなど、政策的な枠組みづくりが進んでいます。今後は温暖化に対して非常にもろい地域において、適応基金を活用した適応対策プロジェクトが進められていくと考えられます。
われわれ人間の活動が原因で引き起こされたと考えられる地球温暖化は、本来責任のない将来世代に対する「負の遺産」です。こうした遺産の次世代への引き継ぎを最小化するために、地球温暖化「緩和」策は根本的な対策として重要です。一方で、着実に進行する温暖化がもたらす被害を現実のものとして受け入れ、被害を最小化する「適応」策の意義も、今後さらに注目されるべきでしょう。
機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。
お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。