所属部署 経済グループ
氏名:越智小百合
交易利得・損失(Trading Gains/Losses)とは、ある基準年から交易条件が変化することによって生じる、国内居住者の実質購買力(実質所得)の海外からの流入、あるいは海外への流出のことです。交易条件は、一定の輸出量と交換に購入できる輸入量が基準年と比べて何倍になっているかを表し、(輸出価格指数/輸入価格指数)で求められます。この値が小さくなることを、交易条件の悪化といいます。 近年、原油など資源価格高騰により交易条件が悪化しており、2008年度4〜6月期には年率28兆円(実質GDP比5%)の交易損失が発生しています。その分、国内居住者の実質購買力(実質所得)が海外への流出しているわけで、内需を抑制する要因として注目を集めています。 しかし、「2008年度4〜6月期の実質GDP564兆円(年率)のうち28兆円が資源高により失われた」といった評価の仕方は適切ではありません。*1 交易は売り手と買い手の双方に利得があるからこそ行うものであって、交易からどちらかが損失を被ることはありません。基準年を示さずに交易損失の金額の大きさを強調し、あたかも交易によって損失が生じているかのように評価することは適切ではないのです。現在、内閣府の国民経済計算は基準年を2000年と定めていますが、もしこれが2008年であれば、2008年の交易損失はゼロ、2000年の交易利得が28兆円になるのですから、交易利得・損失の数字は基準年とセットで読むことが大切です。つまり、「2008年4〜6月期の交易条件が基準年2000年から不変(1倍)であったなら得られたであろう実質購買力(実質所得)が、実際には交易条件が0.68倍に低下(悪化)したため年率28兆円の実質購買力(実質所得)が国内居住者から海外へ流出した」と評価することが適切です。
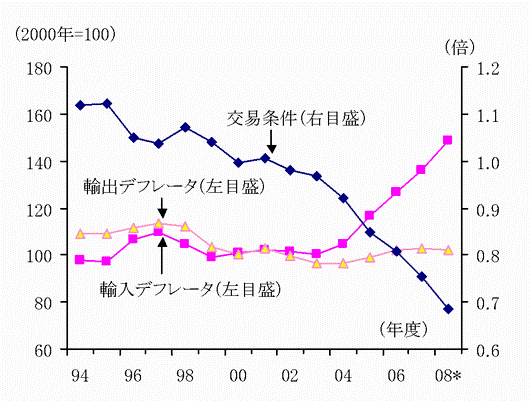
図表1.交易条件
* 08年度は4〜6月期の値資料:内閣府「国民経済計算」より(日立総研)作成
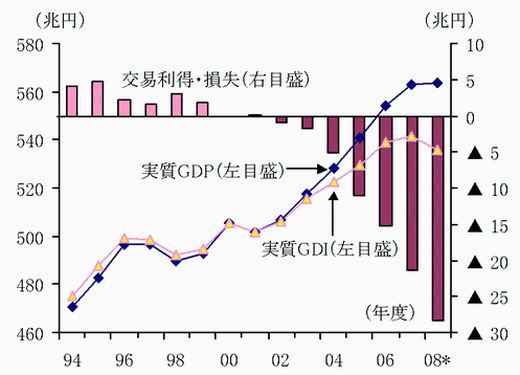
図表2.交易利得・損失(=実質GDI−実質GDP
* 基準年は2000年、08年度は4〜6月期の値(年率)資料:内閣府「国民経済計算」より(日立総研)作成
概念としては、交易利得・損失は(実質GDI)−(実質GDP)として定義されます。GDP(Gross Domestic Product:国内総生産)とGDI(Gross Domestic Income:国内総所得)は、どちらも一国の経済規模を測る指標です。生産したものは支出され、支出の受け取りは所得となるため、両者は名目値では必ず等しくなります。いわゆる三面等価の原則です。しかし、交易条件に変化が現れた環境下では、実質GDPは生産量(支出量)を表すのに対し、実質GDIは実質所得、すなわち実質購買力を表すため、両者は実質値では異なる値を示します。その差が交易利得・損失分になります。
仮想例として、以下の図表3のように自動車という一財のみを生産、消費、貿易している世界を想定します。基準年の2000年、日本は80台の自動車を生産し、うち30台を海外へ輸出。また、海外から20台の車を輸入。内需は70台(=国内総生産80−輸出30+輸入20)とします。また、価格面では2000年に、輸出入、内需のすべてにおいて、車は1台100万円で取引されていたとします。それが、2008年、台数は不変。価格も輸出価格は不変で、輸入価格のみが400万円に4倍に跳ね上がったとします。

図表3.日本の生産、貿易、内需の想定
以下のように定義すると、「総需要=総供給=総所得」の関係が名目値でも実質値でも常に成立します。
「総需要=内需+輸出」
総需要は、内需と海外居住者の日本製品への需要である輸出を足したものになります。 「総供給=国内総生産(GDP)+輸入」
総供給は、日本国内で生産し供給されるもの、そして海外から輸入し日本国内へ供給されるものを足したものになります。
「総所得=国内総所得(GDI)+海外が受け取る所得」
総所得は、国内総生産により日本国内居住者が受け取る所得と、日本への輸出で海外の人が受け取る所得を足したものになります。
基準年の2000年の総需要、総供給、総所得は、以下の図表4のようになります。名目値は金額で表していますが、実質値は台数で表しています。これは、実質購買力を台数で表すことで、基準年からの交易条件の変化により、車何台分の実質購買力が海外に移転したのかを理解しやすくするためです。実質値を名目値と同様金額ベースで読みたい場合は、実質値(台数)に、100万円を掛けます。2000年は、名目GDP=名目GDI(=8,000万円)が成立します。そして、基準年は交易条件に変化がないので、実質GDP=実質GDI(=80台)が成立します。
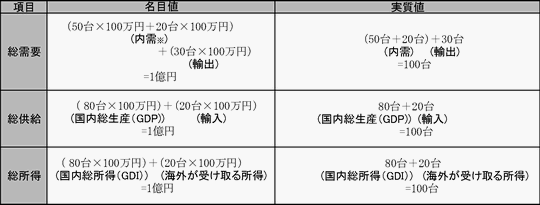
図表4.2000年(基準年)の総需要、総供給、総所得の名目値と実質値
* 内需の内訳は、50台が国産車、20台が輸入車注:実質値は台数ベース。金額ベースは100万円/台を掛けることで求められます。
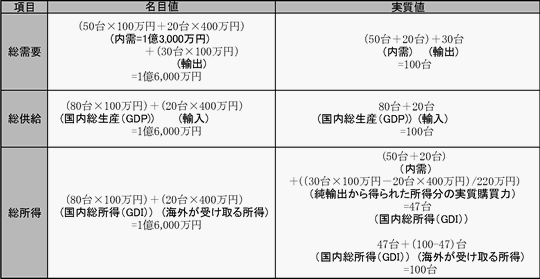
図表5.2008年の総需要、総供給、総所得の名目値と実質値
* 実質値は台数ベース。金額ベースは100万円/台を掛けることで求められます。
一方、交易条件に変化のあった2008年では、上の図表5のように、名目GDP=名目GDI(=8,000万円)は成立するものの、実質GDP=実質GDIは成立しません。名目GDI(8,000万円)の実質購買力、つまり、8,000万円の所得で何台の車が買えるのかを表す実質GDIはどう計算したら良いのでしょうか。まず、内需として1億3,000万円で70台の車を実際に買っていることから、この70台を1億3,000万円分の実質購買力として認めます。次に、名目GDI(8,000万円)との差額−5,000万円、これは純輸出から得られた所得−5,000万円(=30台×100万−20台×400万)でもありますが、その実質購買力を計算します。この場合、符号がマイナス、つまり、所得(8,000万円)以上に買った(1億3,000万円)のですから、その分を差し引くために内需の平均価格186万円(=1億3,000万円/70台)で割って、−27台(=−5,000万円/186万円)とするのが自然なようにも思われます。しかし、ここでは符号がプラス、つまり所得以下しか買わなかったかのように計算してみましょう。すでに内需として買った車以上に車を買うには、輸出していた車の輸出をやめて買うか、追加で輸入して買うことになります。であれば、輸出車と輸入車の平均価格220万円(=(30台×100万円+20台×400万円)/(30台+20台)=1億1,000万円/50台)で割るのがよさそうです。−5,000万円/220万円=−23台となり、純輸出から得られた所得−5,000万円は−23台分の実質購買力という計算になります。内需(1億3,000万円)分70台と合わせた47台(=70台−23台)が、名目GDI(8,000万円)の実質購買力、つまり実質GDIです。したがって、交易利得・損失=実質GDI(47台)−実質GDP(80台)=−33台となります。基準年以降の輸入価格の高騰によって、日本国内居住者の実質購買力33台分が海外へ移転(海外の実質購買力20台→53台)したというわけです。
上記の例のように、実質GDIと実質GDPは内需分は同じですので、その差である交易利得・損失は純輸出分だけです。国民経済計算では、以下の式が用いられています。*2
交易利得・損失=(X−M)/P−(X/Px−M/Pm)
P=(X+M)/(Xr+Mr)
X:名目輸出、M:名目輸入、Px:輸出価格指数、Pm:輸入価格指数
P:ニュメレールデフレータ、Xr:実質輸出、Mr:実質輸入
先ほどの計算と同じく、Pは輸出+輸入の平均価格(輸出入デフレータの加重平均)を用いています。
P=(30台×100万円+20台×400万円)/(30台+20台)
=1億1,000万円/50台=220万円となり、
これを代入すると、
交易利得・損失=(30台×100万円−20台×400万円)/220万円−(30台−20台)
=−5000万円/220万円−10台=−33台
となり、先ほどの計算と同じになります。
ニュメレールデフレータに、内閣府の国民経済計算では、輸出入デフレータの加重平均を用いていますが、他にも内需デフレータ、GDPデフレータ、輸入デフレータなど複数の候補を国連の定めた国民経済計算体系である93SNAは認めています。純輸出(X−M)の符号がプラス傾向であれば、輸出入デフレータの加重平均か輸入デフレータが適当で、逆に符号がマイナスであれば、内需デフレータが適当なように思われます。日本はニュメレールデフレータに輸出入デフレータの加重平均を採用していますが、それは純輸出が黒字傾向にあることを背景に選択されたものと考えられます。
機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。
お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。