所属部署 経営グループ
氏名:山下幸慈
「倒産隔離(Bankruptcy Remoteness)」とは、証券化*1による資金調達の際に、資産の原保有者(以降「オリジネータ」)の倒産などから、譲渡された資産や証券化スキームが影響を受けないようにすることです。図表1は基本的な証券化スキームを示したものです。証券化では、(1)オリジネータが保有する資産を特別目的事業体(Special Purpose Entity、以降「SPE」)などに譲渡し、(2)SPEは資産が生み出すキャッシュフローを原資として投資家に証券を発行して、(3)オリジネータに支払う売却代金を資金調達します。
銀行借入や社債が企業の信用力を裏付けとした資金調達であるのに対して、証券化は資産が生み出すキャッシュフローの信用力を裏付けとした資金調達であるため、倒産隔離によって資産や証券化スキームを破たんリスクからいかに切り離すかが重要となります。具体的には(1)オリジネータが破たんした際、資産やSPEが影響を受けないようにすること、(2)証券を発行しているSPE自体が破たんしない仕組みを作ること、そして(3)オリジネータとSPEが実質的に切り離されていることが必要となります。
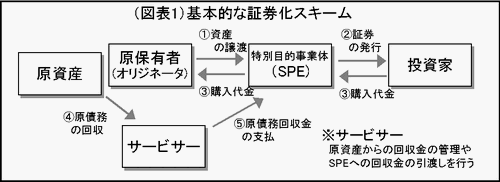
倒産隔離が実現されていない場合、その資金調達は資産をもとにした証券化ではなく、資産を担保とした借入としてみなされます。担保取引としてみなされると、万一オリジネータが破たんした場合にはSPEは他の債権者と同等の地位におかれ、資産から生み出されるキャッシュはオリジネータの管財人などに取り込まれる可能性があります。結果、投資家は証券の購入代金を回収できないリスクが高まります。過去、大手スーパーA社が会社更生手続きを申請し、同社がオリジネータとなった商業用不動産ローン担保証券が国内初の債務不履行となるのではないかと危ぐされたケースがありました。A社の管財人は「実質的には店舗を担保にした資金調達の可能性がある」として、更生計画にもとづいてSPEに支払われる不動産賃借料のカットを主張しました。しかしながら結果的には、賃借料は債権カットの対象とならないことで決着し、本証券化商品は債務不履行を免れました。
このケースはオリジネータの破たんによる倒産隔離が問われたケースでしたが、倒産隔離の実現には、オリジネータからSPEへの資産譲渡が形式的でなく正しく行われた売買である必要があります。これを「真正売買」といい、その条件として(1)当事者の意思、(2)譲渡価格の妥当性、(3)譲渡にかかる対抗要件の具備*2などが必要とされます。
証券化スキームにおいて破たんリスクは、オリジネータだけでなくSPE自体にもあります。万一SPEが破たんしてしまうと原資産から生み出されたキャッシュは、投資家の手元には届きません。これを避けるためSPE自体を破たんさせない仕組みを作ることが重要です。
SPE自体を破たんさせないための方策としては、(1)倒産予防措置として兼業を禁止するためにSPEの定款の事業目的を証券化商品の発行のみに限定するなどの措置、(2)倒産手続きを行うことを制限するために取締役会の破産申し立て決議に取締役会全員の賛成を要する旨を定款に規定したうえで、取締役の一人に公認会計士などの中立的な立場の人を置くなどの措置がとられるケースがあります。
SPEは原資産を譲り受けるためだけの器であり、原資産から生み出されるキャッシュの回収もSPEは行わずサービサーに回収業務を委託します(図表1参照)。
このように倒産隔離を実現する上で、オリジネータの破たんリスクや、SPEの破たんリスクが形式的ではなく実質的に切り離されることが重要であり、これまでさまざまなケースを踏まえ実務主導で法整備やルールづくりが行われてきました。
サブプライムローン問題に端を発した未曾有の金融危機の中、企業の破たんリスクも顕在化しており、倒産隔離の重要性も高まっています。証券化が持つ企業の信用力ではなく資産のキャッシュフローに依拠した資金調達機能を活かし投資家の信頼を高めるためにも、引き続き実態に即した法律的、会計的なルール作りが必要となるでしょう。
倒産隔離は、関係者の破たんリスクからSPEを切り離すことが重要ですが、オリジネータとSPEとが形式的ではなく実質的にも切り離されていることも重要です。
大手小売店B社が過去行った本店ビルの証券化において、証券化の会計処理を見直し過年度の決算訂正を行うと発表するケースがありました。理由は、オリジネータとSPEである特別目的会社とが実質的に切り離されていないことによるものでした。不動産の証券化では、オリジネータが特別目的会社に不動産時価の5%を超えて出資していた場合、会計上のオフバランス処理が認められず、資産を担保とした借入としてオンバランス処理が求められます。B社は形式的には特別目的会社に5%を超えない範囲で出資をしていましたが、他の出資会社の中にB社の社長(当時)が実質株主となるC社が含まれており、更にC社は資金調達の際に社長(当時)から担保提供を受けていました。B社とC社とを合算すると特別目的会社への出資は5%を越えるため、オフバランス処理から借入によるオンバランス処理として決算を訂正することになりました。
機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。
お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。