所属部署 経済グループ
氏名:飯塚知子
里山は日本の国土の約4割を占め、そこには絶滅危惧(きぐ)種の生息する地域の約半数が含まれている*1ともいわれています。生物の多様性を維持していく上で極めて重要な場所です。
環境省は里地里山を「集落を取り巻く農地、ため池、二次林と人工林、草原などで構成される地域であり、相対的に自然性の高い奥山自然地域と人間活動が集中する都市地域との中間に位置する」と定義しています*1。
主に二次林などを里山、それに農地などを含めた地域を里地と呼ぶ場合が多いようですが*2、ここでは里地里山すべてを含めて里山の一語で呼ぶこととします。
自然を壊すという言葉を聞くと、まず人間が介入するということを思い浮べますが、里山の発想では反対に、人間が介入することによって自然資源や生物多様性が維持されると考えます。日本の例でいえば、豊かな田園があってこそ多様な水生動物やそれをえさとする鳥類などによって生態系が保たれ、人間を含めた生物の生存の持続性が保たれているといえます。
今この里山が荒廃の危機に直面しています。その原因は大きく分けて2つあります。1つ目は農林業の縮小による良質な田園や手入れされた森林の減少、2つ目は人口の減少や高齢化による里山環境維持の担い手不足です*3。
1992年に国連地球サミットで採択された生物多様性条約を契機として、国レベルでは環境基本法の制定(1993年11月)や生物多様性国家戦略の閣議決定(第一次(1995年10月)、第二次(2002年3月)、第三次(2007年10月)、生物多様性国家戦略2010(2010年3月))がなされ、地方自治体レベルでも里山の保全や活用に関連する条例が制定されています。補助金や独自課税などの施策も含めて保全活動は全国各地で行われており、里山再興に向けた積極的な取り組みが始まっています。例えば、兵庫県豊岡市ではコウノトリの復活を命題として環境維持に向けた取り組みを開始しています。農薬や化学肥料に頼らない農業をはじめ、田んぼや河川の自然再生、湿地の再生、森林の整備などを実施してコウノトリのえさとなる多様な生き物を育みながら、コウノトリが生息できる地域づくりを目指しています。それと同時に地域ブランド作物の販売や大手旅行会社主催のツーリズム受け入れなどを行い経済活性化も図っています。
これら里山再興への参加主体は多様で、地元住民や農林業者、NPO、企業、研究機関、自治体、各省庁などさまざまな組織や専門家がかかわっています。また、その数自体年々増加しています。例えば、森林ボランティア団体数は1997年277団体から2008年 2,357団体へと約8.5倍に増え、また森林整備などを目的として独自課税を行う自治体の数も2003年の制度導入以来、全国30県にまで拡大しています。さらに、大手企業でもCSRの一環として植林活動などを行う動きが広がっています。まさに、地域や組織を越えて人の交流と資金の調達が進み出しているといえます。
このように近年里山の再興に向けた取り組みは進んでいるものの、里山を類型別に見た場合、比較的都市部に近い地域に活動が偏っているのが現状です。今後は高齢化率や第一次産業率が高い山間地域での取り組みを強化していく必要性が指摘されています(表1)。都市地域と過疎地域間の連携・協働による広域的な里山活動の促進、特に地球温暖化対策としても注目度の高い森林整備を進めていくことが課題になると考えられます。
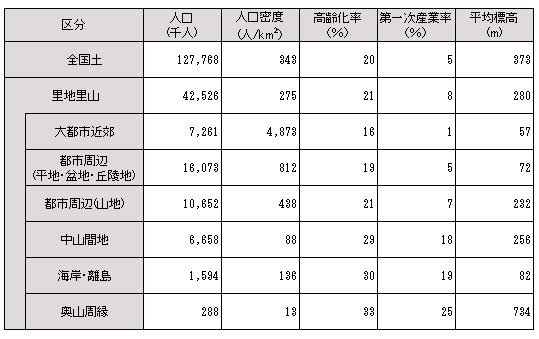
表1:里地里山の各類型区分における社会的状況および標高
資料:環境省里地里山保全・活用検討会議「平成20年度第3回検討会議 資料2全国の里地里山の現状分析」、「平成17年国勢調査」より日立総研作成
以上のように、生物多様性保全や地域振興の観点から里山に注目が集まっている中、2010年10月に生物多様性条約第10回締約国会議(以下、COP10*4)が名古屋市で開催され、日本は「SATOYAMAイニシアティブ」を世界に提案する予定になっています。
「SATOYAMAイニシアティブ」は環境省と国連大学高等研究所が提唱している取り組みで、自然資源の持続可能な管理と利用のための共通理念を構築し、世界各地において自然共生社会の実現に生かしていこうという試みです。具体的には、日本をはじめ海外でもみられる里山の事例を収集し、各地域の取り組みや共同体の役割を分析します。そして、里山的な環境を保全する活動の技術的支援に生かすとともに、他の地域への波及・普及を図ることを目的としています。
一方、COP10の主要議題には(1)生物多様性の損失速度減少に関する「2010年目標*5」の達成状況の検証と新たな目標の策定、(2)「遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)*6」に関する国際的な枠組みづくりの2つが掲げられています。これに加えて、関係者の間で関心を集めているTEEB(生態系と生物多様性の経済学)*7の最終報告書では、生態系や生物多様性が損なわれることによる経済的・社会的損失の程度や、その危機に対する具体的な対処方法がステークホルダーごとに示されることになっています。
「SATOYAMAイニシアティブ」によって、里山で培った日本の経験を日本の強みとして世界に発信する中で、里山の概念やその保全の取り組みがどのように形を変えながら世界に浸透していくか、反対に生物多様性に関する世界の潮流が日本国内にどう流れ込んでくるのか、今後の動向が見逃せません。
また、アルファベット化したSATOYAMAが、世界に誇る日本の環境概念としてMOTTAINAIに続く言葉となり得るかどうかに注目が集まっています。それには、国内の機運の高まりも重要です。
皆さんもまずはこの週末、近くの里山に出かけてみてはいかがでしょうか。
機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。
お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。