所属部署 産業グループ
氏名:佐藤大輔
メディカルツーリズム(Medical tourism)とは、患者が医療を受けるために他国へ渡航することです。メディカルトラベル(Medical travel)、ヘルスツーリズム(Health tourism)などともいわれています。他国へ渡航する理由の大部分は高度な医療または高質な医療を受けるためですが、低コスト、アクセス時間の短縮化などを理由とする場合もあります。
世界的にメディカルツーリズムは拡大傾向にありますが、ブラジル・インド・タイ・シンガポールなどの医療機関は、米国における国際的な病院品質の認証機関であるJCI(Joint Commission International)の認証を取るなどして外国人患者の受入れ拡大を図っています。
メディカルツーリズムは国によって、その位置付けはさまざまです。タイとシンガポールは、ともにメディカルツーリズムの先進国と言えますが、タイは外国人を国内に呼び込むという観光誘致目的が色濃く、シンガポールは医療技術維持や競争的環境醸成による医療の質の向上を狙ったものであり、病院経営の一環として取り組まれてきています。
日本の医療技術は、心臓病による死亡率がOECD諸国で最も低く、前立腺がん死亡率もOECD諸国で最低水準であるなど、世界的にも高く評価されています。また医療機器分野でもMRIやCTという高度医療機器の普及度合いも世界最高水準にあります。さらに世界のどの国も経験したことがない高齢化社会を迎えつつあり、医療サービスは私たちにとってもより身近なものとなっており、産業としての重要性はますます高まっていくと思われます。決して資源が豊富といえない日本にとって、医療サービスに対する海外からの需要を取り込むメディカルツーリズムは国内医療周辺産業を活性化させ、日本経済の成長に大きく貢献する可能性を持つものといえます。症例数の増加による先進医療の発展、獲得した資金の国内医療設備などへの再投資、国内外のマーケット拡大で醸成される競争的環境の中で促進される医療機器・医薬品などの関連産業の国際競争力強化などもメリットとして挙げられています。
日本政府は、2009年12月30日に「新成長戦略(基本方針)」、2010年6月18日には「新成長戦略」をそれぞれ閣議決定していますが、医療・看護・健康関連産業を「ライフイノベーションにおける健康大国戦略」の中で日本の成長けん引産業として位置付けています。その具体的取り組みの一つとして、「アジアの富裕層などを対象とした健診、治療等の医療及び関連サービスを観光とも連携して促進していく」としており、メディカルツーリズムという言葉はないものの、日本の成長戦略の一部を担うビジネスとして大きな期待を集めていることが読み取れます。
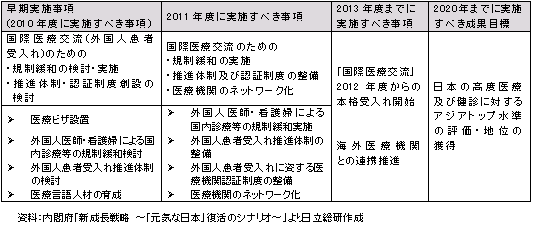
表 健康大国戦略における医療の国際化推進の工程表
これと前後して、各省庁もメディカルツーリズム推進に対応する活動を進めていますが、経済産業省は2010年2月から約1カ月にわたり実証事業を実施し、先進国の実態調査や中国・ロシアなどの潜在市場ニーズ調査を行う一方、24名の外国人患者を国内9つの医療機関で受入れ、医療機関とメディカルツーリズムにかかわる業者(旅行代理店・ホテル・通訳・医療アシスタンスなど)に求められる機能検討を行いました。
新成長戦略の工程表にもあるように、日本におけるメディカルツーリズムの発展のためには、医療ビザの新設、医療機関を中心とした異文化・多言語化など受入れ支援体制の強化、というようなインフラ整備を急ぐ必要があります。現時点では、外国の患者にとって日本の医療サービスを認知する機会自体が非常に少ないため、外国人患者からの需要喚起が必要であり、また、受入れの際に、言葉の問題を顕在化させないようにしつつ、観光サービスを医療サービスと連携しながら顧客要望に沿うように提供するなどの推進体制を整備する必要があります。
また、これら以外の課題として、法的リスク逓減のための契約書の整備、アフターフォロー体制の構築などを挙げることができます。例えば、外国人患者が帰国してからもその問い合わせへの対応などが十分に行える体制・仕組みを整えるべきでしょう。
メディカルツーリズムは、2020年の潜在需要5,500億円、経済波及効果2,800億円が期待できると日本政策投資銀行は試算していますが、その発展と現代医療が抱える課題を切り離して考えることはできません。
日本の病院の約7割が赤字経営に苦しんでいますが、日本医師会の中川俊男副会長は2010年6月30日の定例記者会見で、メディカルツーリズムの恩恵を受ける"勝ち組医療機関"の方に、そうでない医療機関の医師が引き抜かれることを危ぶむ主旨のコメントを出されています。また、外国人患者の診断・治療に重点が置かれるようになり、日本人患者の待ち時間が長くなるなどの弊害も生じる可能性があります。
メディカルツーリズムの発展は、国民皆保険の下で病院間の競争原理が働きづらかったこれまでの日本の医療にとって大きな転換点になるのか、この転換を受容した場合の日本の医療像とはどのようなものに変容していくのか。ビジネスチャンス拡大への期待はありますが、医療サービスを受ける国民としても、今後の動向を注視する必要があります。
機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。
お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。