所属部署 研究第四部国際グループ
氏名:大矢好彦
「ペルチェ素子」とは、熱エネルギーと電力を直接変換することができる電子部品で、従来は主にコンピューターのCPUなどを冷やす部品として使われていました。近年、振動や室内の照明光、機器の廃熱や体温などを利用した微小量の環境発電に注目が集まっています。従来の熱電変換システムは、蒸気タービンなど大型サイズのものしか存在しませんでした。一方で、ペルチェ素子は数ミリ〜数センチ角の微小サイズで熱を電気に変換することができることから、熱電変換モジュールとしての活用に注目が集まっています。
ペルチェ素子の特徴は、温度差1℃程度の熱源と素子さえあれば発電可能なことにあります。例えば、無線センサなどへペルチェ素子を電源として搭載すれば配電線の敷設や電池の交換などの作業なしに発電が可能なため、コストを削減することができます。また、これまでの発電設備に比べると、設置場所の制約も少なくなります。
ペルチェ素子は従来、発電力の不足が最大の問題とされていました。地熱・温泉熱利用分野での実用化には、変換効率が10%を超える必要があるとされていましたが、2000年前後より同性能を満たす性能を有するもの*1が多数開発されています。さらに、無線センサなどのセンシングデバイス分野でも、10年前には1mWレベルの電力が必要だったセンサが1/100mWレベルでも稼動するようになるなど、問題が解消されてきています。
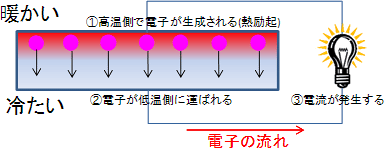
資料:日立総研作成
図1:熱電変換の仕組み
ペルチェ素子は、熱電変換モジュールとして、(1)1/1,000mW〜mWレベルの発電量となるセンシングデバイス分野、(2)100W〜kWレベルの発電量となる産業用廃熱分野、 (3)kW〜レベルの地熱・温泉熱・太陽熱利用分野の3つの分野での成長が期待されています。
センシングデバイス分野は、ドイツや日本を中心に研究開発が進められ、KELKや高木製作所などで製品化を始めています。また、ドイツのマイクロペルト社は2011年6月に世界初となる熱電発電デバイス専用の量産工場を開設しています。温度モニタリングなどを行う無線センサモジュールや、体温を熱源とした医療機器への電力供給用としての利用が期待されており、2020年までにはペルチェ素子を搭載した医療機器が登場すると予測されています。*2
産業用廃熱分野は、日本や欧米を中心に研究開発が行われています。昭和電工やコマツなどでは、焼却炉や工業炉での廃熱利用を2015年前後の実用化を目標に開発が進められています。また、GM、トヨタ、BMWなどの自動車メーカーや、GEやSiemensなど欧米大手企業では、自動車の廃熱利用の研究開発が進められています。
地熱・温泉熱・太陽熱利用分野は、ドイツの研究機関を中心に世界各国で研究開発が行われています。日本では、東芝などが温泉施設にて実証実験を進めています。さらに、パナソニックは同分野での利用を想定し、配管型の熱電変換モジュールを開発しています。
ペルチェ素子の適用分野は、比較的小規模な発電であり、大規模発電を完全に代替するものではありません。しかしながら、コンパクトでかつ簡単な仕組みであることから、配線が困難な場所への電力供給や、従来システムとの組み合わせによって燃費やバッテリーの性能向上を実現するものとして期待されています。
機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。
お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。