所属部署 研究第五部 中国分室
氏名:陳嘉琦
従来より中国では、「営業税」と「増値税」がともに流通課税として企業に課されてきました。「営改増」は従来の営業税を撤廃し、増値税に一本化する税制改革です。これにより、サービス業における仕入れコスト分への課税が控除され、企業の税負担を軽減できると見込まれています。この税制見直しは2011年11月17日からスタートしています。
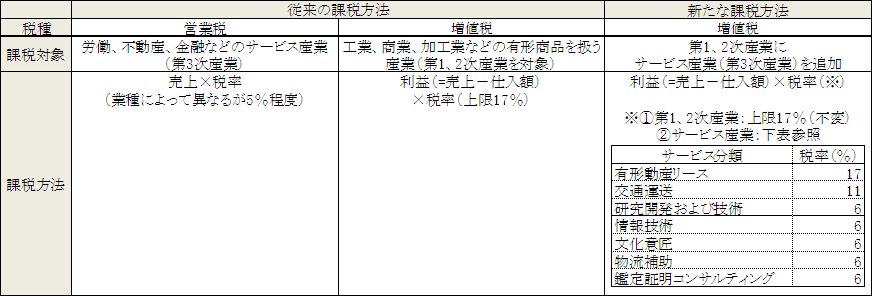
具体的には、例えばある研究会社A社が市場調査業務をB社に委託したとします。A社の売上は100万元、委託費用(=仕入額)は40万元とした場合、「営改増」前には営業税で5万元(100万元×税率5%)の納税義務がありました。しかし、「営改増」後には増値税で3.6万元(60万元×税率6%)の納税となり、1.4万元の減税となります。
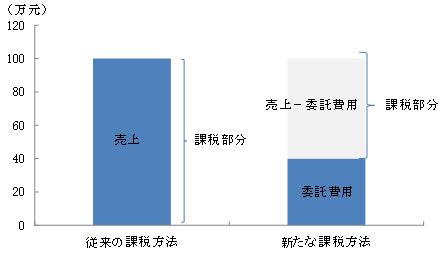
図 「営改増」前後の比較(例)
過去数十年、第1次産業、第2次産業は中国経済のけん引役でした。特に、第2次産業では国内の安い人件費を武器にした、低コストでの2次製品加工とそれらの輸出が主体となり、中国は「世界の工場」と呼ばれてきました。しかし、人件費の上昇に伴い低コストという競争優位性が薄れつつあり、産業発展の中心軸はサービス産業(第3次産業)にシフトしつつあります。2011年の中国GDPに占めるサービス産業の割合は46%であり、韓国の1980年、日本の1970年レベルに相当します。中国政府はサービス産業の発展を視野に入れた税制改革を推し進めています。
2011年10月、中国国家国務院常務委員会議で「営改増」の実施が決定されました。2011年11月には、財政部および国家税務総局より「『営業税から増値税への試行方案』を印刷配布することについての財政部、国家税務総局による通知(財税[2011]110号文)」と「上海市で交通運輸業および一部の現代サービス業にて営業税から増値税への試行を実施することについての通知(財政[2011]111号文)」が発表されました。それに基づき、2012年1月1日からは「営改増」の試行が上海市で開始されました。2012年6月までに上海市の13.9万社の企業が減税メリットを享受し、減税総額は44.5億元(約534億円)に達しました。特に、中小企業は平均約40%の税金負担を軽減されています。さらに2012年7月には、中国国家国務院常務委員会にて「営改増」実施範囲の拡大が決定されています。9月1日から北京、10月1日から深セン、安徽省、江蘇省、11月1日から広東省、厦門、福建省、12月1日から天津、浙江省、湖北省など、2012年末までには合わせて10省・市にて「営改増」の適用が拡大され、2015年までには全国規模にまで拡大する目標です。北京市の試算によると、北京の対象納税企業は13.8万社となり、年間減税総額は約165億元(約2,000億円)に達する見込みです。
中国政府は、内需拡大など産業構造転換政策の一環として第3次産業の発展促進を目指し、今回の税制改革を実施しています。企業の課税負担を減らすと同時に消費拡大を図り、需要を喚起する狙いもあります。サービス産業拡大に向けた税制改革が実施されることにより、今後ますます中国の第3次産業比率は拡大していく見込みです。売上課税から利益課税に移行することは企業にとってメリットがあるだけでなく、中国の税制が世界的に見ても一般的な課税方式へ移行することを意味しています。
機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。
お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。