所属部署 研究第二部 産業グループ
氏名:沖林久徳
Condition Based Maintenance(以下、CBM)は「状態基準保全」とも呼ばれ、「現在、安定稼動している設備に対して、不要な機器交換などのメンテナンスを行うのではなく、必要と判断された時にのみ実施する」予防保全の考え方です。従来保全の考え方は、機器が故障した後に修理する「事後保全(Breakdown Maintenance)」から、故障を事前に予防するため一定の時間間隔でメンテナンスを実施する「時間基準保全(Time Based Maintenance。以下、TBM)」へと主流が移って来ていました。これに対してCBMは、これからの新たな予防保全の考え方として注目が高まっています。
CBMの考え方自体は1970年代に普及していましたが、故障診断に用いるデータを収集するセンサの設置やデータ解析用の計算機など、設備の導入費用が高価であったことや、想定故障を算出する処理の煩雑さなどの観点から、当時としては広く実用化されるに至りませんでした。
近年のICT技術の進歩に伴ってデータを駆使した合理的な保全が可能になり、現在CBMは、さまざまな設備・機器、産業プラントに適用されてきています。例えばGEは、ガスエンジン、風力発電用タービン、航空機(ボーイング社と共同)などに実績があります。また、トンネル、橋、道路といった社会インフラに対して、老朽化や異常検知といった設備状態の見える化を行い、CBMを実施するための状態監視・予兆診断をサービスとして提供するビジネスも展開されつつあります。
Industrie 4.0、Industrial Internetといった、IoT(Internet of Things)技術を利活用した産業革新が社会産業システムに本格的に浸透しつつある中で、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)により精緻化したセンシング技術やビッグデータ解析技術のさらなる高度化によるCBMの進展が期待されています。
機器の故障率の時間的推移は、(1)初期故障期、(2)偶発故障期、(3)磨耗故障期、の3つの期間に分けられ、バスタブ曲線(図1)として知られています。従来は製品寿命などの機器仕様に応じ、TBMにて磨耗故障前の定期交換によるメンテナンスを実施することで、設備の信頼性担保・向上を図っていました。しかし、交換に伴う初期不良によるトラブルといった保守不良が多く発生(故障原因の約3割が保守不良によるという報告もあります)し、問題となっています。
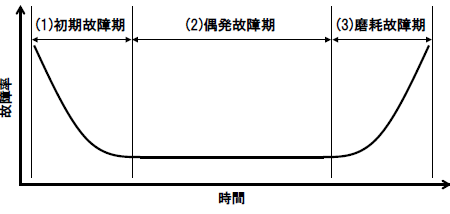
図1 機器の使用時間と故障率の推移(バスタブ曲線)
またTBMでは、機器が安定稼動している偶発故障期にメンテナンスを行うことで、磨耗故障期の急速な故障率上昇による機器停止などを未然に防ぐことに主眼がおかれています。しかしながら、安定稼動をしている低故障率の期間にむやみにメンテナンスを行うことで、交換によってかえって故障率を悪化(初期故障期の高い故障率へ移行)させてしまう恐れもあります。すなわち、メンテナンスを実施しているにも関わらず、設備全体としての信頼性が下がってしまうことになりかねません。
一方CBMでは、センサなどから収集したデータなどから設備の稼動状況を監視・分析し、異常の兆候(予兆)を発見した場合にのみ保守作業を実施します。このため、上記のような保守不良によるトラブルや信頼性の低下を防止できるだけでなく、設備保有者にとっては、不要な整備や部品交換などが発生しないことで保守コスト削減、さらには機器の長寿命化による資本的支出(CAPEX)の削減も図ることが可能になります。
今後TBMの一部がCBMに代替されるケースが増えていくことが予想されます。定期点検事業を主な収益源としているメンテナンス企業などは、施設監視データ解析サービスビジネスへ参入するなど、将来的な事業転換の必要性が高まるものと考えられます。また、既に部分的にCBMが取り入れられている原子力発電所、昇降機などの分野におけるCBMの適用範囲の拡大や、保守対象となる複数の設備拠点を一括監視・分析する、メンテナンスセンタサービスビジネス(SaaS、PaaS(注)など)のニーズが高まる可能性があります。
国内の社会インフラは、2030年ごろには設備の半数以上が耐用期限を迎え、インフラ保守ビジネスはますます重要性を増すことが予想されます。国土交通省は2014年5月にインフラ長寿命化計画を発表し、「必要な対策を適切な時期に、着実かつ効率的・効果的に実施する」ことや、「中長期的な設備の維持管理・更新等に係るトータルコストを低減する」ことなどをうたっています。官民一体となった設備メンテナンス改革の必要性が高まっており、その中でCBMが重要な位置を占めることは明らかです。
先に述べたように、CBMは決して新しい考え方ではなく、複雑なものでもありません。しかしながら、今まで各企業が蓄積してきた「保守ノウハウ・技術」を見える化、あるいは定式化することで、機器故障をシステマチックに分析し、状態監視・予兆診断に生かす必要があります。いわばこれらの「職人技」をいかに精緻にソフトウェア化・システム化できるか、そしてそれを充分な実証(加速試験、寿命予測など)により実運用可能な技術として確立できるかが、CBM関連ビジネスにおける差別化の鍵になると考えられます。センサなどの各要素技術を含めた、今後の技術動向が注目されます。
機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。
お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。