研究活動などを通じ構築したネットワークを基に、各分野のリーダーや専門家の方々と対談
リーマン・ショック以降の世界経済の低成長や政治の不安定化の背景に、ヒト・モノ・カネ・エネルギーが過剰な時代への転換があるととらえ、新たな秩序の必要性を訴えておられる独立行政法人経済産業研究所理事長の中島厚志氏に変化の核心、今後の展望、取るべき対応について伺いました。

独立行政法人経済産業研究所 理事長
1975年 東京大学法学部卒、同年日本興業銀行入行。パリ支店長、パリ興銀社長、執行役員調査部長等を歴任し、みずほ総合研究所(株)専務執行役員チーフエコノミストを経て2011年4月より現職。
その他公職として財務省・財政制度等審議会財政投融資分科会専門委員。
2001年-2011年3月 テレビ東京系列「ワールドビジネスサテライト」レギュラーコメンテーター。
主な著書:
『大過剰 ヒト・モノ・カネ・エネルギーが世界を飲み込む』(2017年、日本経済新聞出版社)、
『統計で読み解く 日本経済 最強の成長戦略』(2013年、ディスカヴァー・トゥエンティワン)、
『日本の突破口-経済停滞の原因は国民意識にあり』(2011年、東洋経済新報社)など
白井:今後の世界経済を展望すると、いくつかのシナリオが考えられます。例えば、「世界経済が成長して先進国、新興国、途上国とも経済果実を得られるインフレシナリオ」です。巨額の財政赤字を抱える日本は、デフレから脱却することが重要課題ですが、すでに金融正常化に向かい始めた米国や欧州に対し、日本はまだ出口が見えません。これほどの財政赤字を抱えてしまうとハイパーインフレにするしかないという声も聞かれますが、現実には、緩やかなインフレにより物価上昇率を2~3%にすれば、実質成長率が1%弱でも名目成長率3%となり財政再建の可能性も見えてきます。
中島:世界経済全体がディスインフレーションにあり、その背景には世界経済の成長力、人口増加率低下の影響があります。また、供給は需要を上回っていますので、緩やかなインフレシナリオで名目成長率を上げて徐々に財政健全化を進めるのは日本の財政赤字への対応において現実的な道筋です。
課題は、世界的なディスインフレの中でどう緩やかなインフレシナリオを実現するかです。欧米では約2%のインフレ率が望ましいとされ、リーマン・ショックの影響で物価上昇率は全体的に鈍化しましたが、サービス価格は上昇しています。日本は原油価格上昇や円安の影響によるモノの物価上昇はありますが、サービス価格はほとんど上がっていません。これは依然デフレマインドが残っているためです。
緩やかなインフレシナリオの実現に、重要となるのは賃金の上昇です。賃金が上がらなければ消費も増えずインフレになりません。賃金を上げて人々のインフレ期待を高めることが必要です。物価が上昇しても賃金が上昇すればペイする、と人々が考えれば値上げへの抵抗感も下がります。
企業も同様です。モノやサービスの値段を上げないことが事業経営の前提のようにみえますが、価格を上げて人件費などを上げても収益につながる形に転換することが重要です。
世界的なディスインフレの中で物価上昇を経済システムにビルトインするには意識を変えることが重要であり、そのためには賃金と物価の連動を軸にした施策が必要です。
白井:経済学者の吉川洋先生(立正大学経済学部教授)は、「高度成長の時代も日本経済は人口増加で成長したわけではなく、イノベーションや企業の力で成長した」と分析されています。その点からも、第4次産業革命、Society5.0などのブレイクスルーにより新たな成長ステージに入ることが、最も理想的なシナリオと思います。AI、IoTなど技術革新の条件もそろっており、課題先進国日本にはさまざまな潜在的ニーズもあります。電気の発明や、自動車の登場に匹敵するイノベーションとなるかはまだ分かりませんが、人々の生活、社会、産業を大きく変える破壊的イノベーションによって成長が加速するシナリオは、描けるでしょうか。
中島:描けると思います。産業革命の歴史をみても、破壊的イノベーションが世界経済の新たな成長につながるときは、社会や消費の仕組みが変わり、今までにない新たな消費やサービスが登場し、それをきっかけに成長が拡大しました。イノベーションを生み出しやすい「仕掛け」をつくることが重要です。
先進国では、消費のウエートが「モノ」から「コト」に移っています。モノの場合は買い替えの頻度を上げることでしか消費が拡大しませんが、コトの場合は蓄積できない分、繰り返し消費の頻度を上げることができ、モノ以上に消費を持続的に伸ばすことができます。企業はこれまでも時代の変化に応じて消費拡大に取り組んできました。人口が増えないから成長できないというのは理由になりません。
その上で、新たなコトの消費とそれに倍するサービス消費を創造する際のポイントは、破壊的イノベーションで社会システムを変えることにあります。第1次産業革命は蒸気機関車の発明で本格化したのではなく、鉄道が整備され、長距離の移動が一般化したことにより、それまで命の危険すらあった大冒険が普通の旅行になり、ホテル業や旅行代理店業なども大きく発展したことに起因しています。今到来が言われている第4次産業革命も、これまでにない社会システムの変革と新たな生活スタイルを創造する「仕掛け」がカギを握ります。
第4次産業革命を盛り上げる先端技術はいろいろ考えられます。自動走行車は、買い物弱者、高齢者、免許を持たない人々の移動の不便さを解消します。自動走行車のエネルギー源として太陽光発電を併せて利用すれば、エネルギーフリーです。自動走行電気自動車をうまく活用すれば、日本中どこにいてもより快適に暮らすことができます。こうした枠組みを築く中で新しいコトの消費が生まれ、配車サービスを利用するなどして新たなサービスの消費が生まれて1人当たりの消費額は今までの枠を超えて伸びます。連鎖する新たな消費が経済の新たな成長につながります。
白井:一方で、「世界経済の秩序が崩れ、経済力が大きい国に都合の良いルールが形成されるシナリオ」も考えられます。第2次世界大戦後のマーシャルプラン以来、世界経済を立て直し、発展を支えてきたのは米国でした。今では中国が世界第2位の経済大国となり、アジアインフラ投資銀行(AIIB:Asian Infrastructure Investment Bank)や、シルクロード基金を設立し、一帯一路構想を推進しています。中国は地政学的利益、経済的利益の追求により、新たな国際秩序を構築しているようにもみえます。これまでの米国中心の経済秩序は、今後どのように変わっていくとお考えですか。
中島:世界経済秩序が変わる可能性は十分あります。
現在は世界の貿易赤字を米国が一手に背負っている状況です。世界の国々は、基軸通貨ドルで国際貿易や海外投資を行っています。しかし、貿易赤字を大幅削減することで米国が世界経済を支えるドルの供給をストップしたとき、ドルの代わりに何を国際決済で使うのか、今のところ解決策はありません。現在、中国は世界一の貿易黒字国で世界第2位の経済大国ですが、人民元がドルに代わる基軸通貨になるとしても時間がかかります。

例えばアジア地域についてだけ人民元を地域の基軸通貨として供給することも考えられますが、その場合中国は今の貿易黒字を恒常的に減らしてでも人民元を供給する経済に転換できるのか、その上で人民元の価値を維持できるのかが問われるでしょう。一時はユーロを準基軸通貨にしようとする動きもありましたが、それにはユーロを世界中に供給し、なおかつ貿易赤字でも成長できるユーロ圏経済にしなければなりません。今日までそれが実現できたのは、世界最大の経済大国でありながら貿易赤字を抱え、それでも成長できる米国だけです。これから中国、ユーロ圏が、米国並みの経済構造をつくれるかが一つのポイントですが、決して簡単ではありません。ただし、一方では海外から財を買い続けて巨額の貿易赤字を計上し続けることには米国経済も限界があります。製造業が空洞化し、雇用が海外に奪われるばかりとの反グローバル的な声も高まっています。難題ではあっても、これからも貿易赤字に苦しむ米国中心の経済秩序を見直す動きが強まっていくでしょう。そして、そのポイントは、貿易赤字を肩代わりしつつ基軸通貨を持つ経済をどこが保有できるかです。
白井:昨年のブレグジット、米国ファーストを掲げる大統領の誕生などに象徴される自国優先の動きを見ると、先進国、途上国ともに余裕がなくなり、「世界経済のパイを長期にわたって奪い合うシナリオ」も考えられます。今後も輸出振興で経済成長をめざす新興国・途上国が、新たに台頭する中で、各国が過度のパイの争奪を避け、社会の安定を保つには何が必要でしょうか。
中島:新興国・途上国の良好な成長を支えているのは、輸出と対内直接投資です。安価な労働力や資源によって外資企業を誘致し、輸出と国内生産を拡大することにより、雇用も拡大します。戦後の日本も、対内直接投資はあまり拡大しませんでしたが、輸出主導型成長モデルで経済成長を果たしました。歴史をさかのぼれば、米国も欧州から貿易黒字を稼いで経済大国になりました。問題は先進国で、世界経済の成長力が鈍化する中で、技術を持つ国内企業の海外移転が増加し、国内の工業基盤が空洞化しつつあることです。

先進国と新興国・途上国の双方が成長しながら世界経済全体を拡大していく方法はいくつか考えられます。2000年代初めのように世界経済全体が大きく拡大するのが理想ですが、最後は米国のサブプライムローンを発端とした巨大なバブルの発生と崩壊をもたらしました。後の時代に悪影響を及ぼす枠組みで成長が高まっても、良いとはいえません。摩擦を増やさず、反グローバルの動きを広げずに、先進国と新興国・途上国がともに成長する一つの考え方は、それぞれ違う国際取引分野にすみ分けして稼ぐ、つまり差別化を図るやり方です。近年の世界貿易の推移をみると、物品(モノ)よりもサービスの貿易が伸びており、先進国のサービス業は生産性が高く競争力があります。サービス貿易の先進国と物品貿易の新興国・途上国で有効な枠組みを組み合わせていくのが手っ取り早いすみ分けでしょう。米国は貿易赤字で不満を募らせていますが、トランプ大統領は経常収支のうち、貿易収支以外の部分、サービス収支や所得収支への不満は口にしません。
新興国・途上国にとって、技術力のある外資企業を誘致して国内で生産してもらうことは大きなメリットがあります。外資企業が新興国・途上国に直接投資し、その収益を本社が所在する国に送金すると、新興国・途上国の所得収支は赤字になりますが、先進国がそれによってサービス収支、所得収支の黒字を伸ばしても新興国・途上国に不満はないでしょう。先進国はこの分野をさらに強めることが成長に結びつきます。
競争力を持つ分野をすみ分けることが貿易摩擦の回避につながり、世界経済のバランスの取れた成長に寄与します。ブレイクスルーで全く新しいモノを創出する、人々が魅力的に感じるサービス・財を提供する、先進国はこうした分野が得意のはずです。従来型のモノの生産は一番効率的で収益が確保できる地域で展開し、先進国は技術開発や新しい仕組みを世界に提供していけば、どの国も満足するでしょう。
白井:中島さんは御著書である「大過剰 ヒト・モノ・カネ・エネルギーが世界を飲み込む(2017年、日本経済新聞出版社)」の中で「ヒト」「モノ」「カネ」「エネルギー」の世界的な過剰を指摘しておられます。
まず「モノの過剰」についてお聞きします。輸出主導型の高度成長を実現した中国に続き、次はインド、さらに他の新興国が続くいわゆる雁行型経済発展*1が進んでいます。輸出が拡大し、供給圧力が高まっているのに対し、先進国を中心とする需要はそれほど拡大していません。日本は新興国からのモノの供給圧力はあるものの、米国ほどの国内製造業の空洞化はみられません。今後、日本のモノづくり、製造業をどのように維持していくべきでしょうか。
モノづくりにかかるコストの中で労働力の割合は低下し、3Dプリンターなどの発達とともに自動化も進みつつあります。近い将来、モノづくりが新興国から先進国に回帰するなど、貿易構造が大きく変わる可能性はあるでしょうか。
中島:日本は、設備投資の対GDP比が主要国の中でもひときわ高い国ですが、ソフトウエア投資の割合は米国の方が高く、その差はどんどん開いています。研究開発投資*2は少し伸びていますが、知財投資*3の伸びは低い状況です。全体で見るとモノづくりの投資には力を入れているものの、ソフトウエアで付加価値を付ける部分では出遅れています。
最適な生産拠点の立地は現在とこれから先とでは間違いなく変わります。条件さえ整えば、産業立地、工場立地が再び先進国に回帰することは十分考えられます。その際、価値の源泉をどこに求めるか、どこに価値のウエートを置くかが重要です。安価な労働力に替わるものとして、何が考えられるでしょうか。例えば3Dプリンターなどは機動性があり、将来大量生産も可能になれば、少品種も多品種も柔軟に製造できます。日本に工場を立地することでコストが削減され、生産性も高くなるのであれば、モノをつくる、サービスを生み出す優位な条件が整います。
しかし、日本企業はすり合わせ、組み立て加工など、世界に誇れる技術は持っていても、これからの産業競争力と付加価値創造につながる知財投資、ソフトウエア投資は十分ではありません。日本企業が、日本を最適立地とする条件を満たす必要十分な投資ができるか、私も関心を持っています。日本の国内市場は飽和しており、いまさら輸出拠点にもしづらいため投資は抑えられてきましたが、投資なくして生産性は上がりません。ハードとソフトの組み合わせなど、変化を取り込んでいかなければ世界の流れについていけなくなります。いつまでも「円安が有利」と考えるようでは、安値で勝負する途上国製造業と同じです。円安も円高も関係なく、オンリーワンの強みを持つ、あるいは生産性の高さで日本に立地することが有利となる条件を構築することが課題です。
白井:「ヒトの過剰」に関して、世界的に人材の流動化が進む一方、国内では大学生の数、労働力人口はともに減少するという、パラドキシカルな状況が起きています。人材に関しては、日本は依然として鎖国状態に近いのかもしれません。移民を受け入れずに大学・大学院卒の高度人材を確保することが可能でしょうか。東京に国際金融センターをつくり、海外から優秀な人材を大勢受け入れる構想もありますが、高度人材の争奪戦が繰り広げられる中で、人材を確保して競争力を高めるにはどのような取り組みが必要でしょうか。
中島:人材の資質に見合った処遇、すなわちポジション、給与所得などの条件をきちんと整えることが必要です。
もし日本が海外の人材を積極的に受け入れる、門戸を開放するとなれば日本で働きたいと考える人は大勢いるでしょう。しかし現状では、日本企業の枠組みが障壁となり、高度人材を獲得しても十分に力を発揮してもらうのは難しいと思います。日本では、総合職の職務規定が確立されていないため、事務職であっても人手が足りなければ総合職の誰かがカバーすることになります。「若い社員は給与が低くて当たり前」という固定観念もあります。ジェネラリストがスペシャリストと仕事する際も、あらかじめ業務の区分けを明確にしておかなければ難しいでしょう。さらに、日本企業はチームで仕事をする仕組みになっています。社内のフロアにいくつかの「島」をつくり、課長の机の前に部下の机を並べるというのは非常に日本的です。人件費の安い時代であれば、一つの「島」すなわちチームで業務を行うことがパワーでしたが、人件費が高くなれば、従来の仕組みは成り立ちません。業務内容を見直して、個々に能力を発揮してもらい、それに見合った処遇を提供すれば効率も上がります。
また、税制の問題もあります。東京国際金融センターは、80年代後半にも実現の動きがありましたが、うまくいきませんでした。いろいろと要因はありますが、今でも日本の税制がネックとなり、高額報酬の金融スペシャリストを呼び込むことが難しいことが挙げられます。今の日本の所得税率では、香港やシンガポールなど税率の低い国に太刀打ちできません。世界の金融トップ人材は必ず統括する部門を持っているので、トップを呼び込めれば部門のチーム全体を呼び込んで力を発揮してもらえます。高度人材を招く新たな枠組みをつくり、法人税だけではなく所得税までをワンセットにした減免が効果的です。もちろん、日本には日本のやり方があるので、高度人材を呼び込むためだけに税制などの制度を全面的に改める必要はないですが、税制や規制を大胆に自由化した中国の経済特区などを例に、固定観念を打破することで競争力を高める施策は考えられます。
もう一つの障壁は、語学力の低さです。IMDというスイスの国際的なシンクタンクの調査によると、日本は語学力の項目で61カ国中最下位でした。外資企業が圧倒的に少なく、対内直接投資残高の対GDP比も世界199カ国の中で最下位クラスです。もちろん、これから改善できる可能性はあります。最近は、訪日外国人が増えて英語を使う機会も増えました。海外に出る機会を増やすことでグローバルに物事を見る意識も高まります。固定観念から抜け出すにはグローバル意識を涵養することも大切です。
白井:日米欧の量的緩和政策により世界中にマネーがあふれる一方、日本に限らず公的部門が赤字を抱える先進国は多く、PFI (プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)やPPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ)などによる民間資金の活用が課題です。最近はフィンテックを活用して金融システムをより効率化する動きもあります。グローバルにマネーがあふれ、ミクロではマネーが必要なところに循環しない、この状況をブレイクし、マネーをうまく循環させる方向に変えるにはどうすれば良いでしょうか。また、個人の貯蓄や企業の内部留保を投資に向かわせる施策は考えられるでしょうか。
中島:日本の場合、政府部門だけが収支赤字です。家計は黒字ですが、実はそれ以上に企業部門が黒字です。個人も企業もお金は持っているにもかかわらず使わない中で、マネーを循環させるためには、お金をもっと使うよう転換させるしかありません。お金は貯めなければ使えませんから、貯蓄も殖やしながら使うということです。個人金融資産の構成をみると、日本は他の主要先進国に比べ預貯金の割合が非常に高く、金融資産の半分以上を占めます。米国は株式の保有割合が高く預貯金は1割、ドイツは3割です。日本はもっと株式保有の割合を高めても良いでしょう。それは、資金運用と調達の両方をバランスよく考えながらお金をどう使うのか、視点を多様化することにもつながります。預貯金は、得る所得の中から貯めるということなので、従業員、つまり被雇用者的な感覚が強いといえますが、株式にお金を使うことは雇用者側、投資家的な感覚になります。株式を保有すると「企業は収益を増やすためにもっと投資すべき」、「国の財政収支は調達と運用のバランスが取れていない」など、良い意味でお金の使い道に対する意識も高まります。

株式市場の構成を見ると、個人株主の株式保有割合は減少しています。少額投資非課税制度(NISA)の導入は、株式投資を始めるきっかけにはなりますが、金額と期間が限定されているので、もっと大胆に制度を変えるべきと思います。「マネー過剰」の時代ほどマネーをいかに得るかよりも金融資産をいかに運用するのかを真剣に考えなければなりません。個人が投資できちんと稼げる形をつくり、より多くの人が投資家の視点を併せ持つことで貯蓄から投資にマネーを向かわせることができます。
規制緩和も有効な施策です。金融機関にはお金を預かる立場とお金を融資する立場があります。融資する立場は強いので、これまではお金を借りる方と預ける方を守る規制強化にウエートが置かれてきました。しかし、お金をスムーズに流通させ、国民を豊かにする、その循環が規制のもとで弱くなりかねない状況も出ています。もちろん、規制緩和により金融業界に強権的な力が生まれたり、預かった資金が不適切な運用で毀損してはならないので、バランス維持は欠かせません。しかし、規制緩和で競争を促進し、フィンテックの新しい仕組みもネット企業に限らず金融機関自らが活用の先兵になるべきでしょう。
米国は、金融規制強化と緩和の繰り返しです。サブプライムローンでは緩和し過ぎた結果、それが引き起こしたバブルと崩壊で世界経済に大きな打撃を与えました。その後は規制が強化された面もあり、バランスが非常に難しいところです。ただ、米国では90年代に「金融機関は21世紀の成長産業」といわれたこともあり、そこまでいかなくとも、良い意味で潤沢なマネーを有効に活用するダイナミックな規制緩和が必要と考えます。
白井:最後は「エネルギー過剰」についてです。米国はシェール革命で世界最大のエネルギー産出国になりました。政治的に安定した米国がエネルギーの覇権を握り、エネルギー関連の地政学的リスクは大きく低下することが期待されます。安い資源を基盤に米国の化学産業の競争力が高まるなど、新しい変化も起きています。
一方、日本は福島の原発事故後、エネルギー政策の国民的合意が難しい状況ですが、再生可能エネルギーの活用や、エネルギー安全保障を考えることは重要です。シェール革命のおかげで世界のエネルギー供給が拡大する新たな環境の中で、日本のエネルギー政策、産業政策はどのように転換すべきでしょうか。
中島:シェールオイルといった非在来型の石油資源が地政学リスクの少ない米国に大量にあるのは、日本のエネルギー安全保障にとって大きなプラスです。輸入先とエネルギー構成を組み替え、再生可能エネルギーの普及にも力を入れる必要があります。再生可能エネルギーはエネルギー源多様化に資するし、近年は価格も下がり採算を取りやすくなっています。
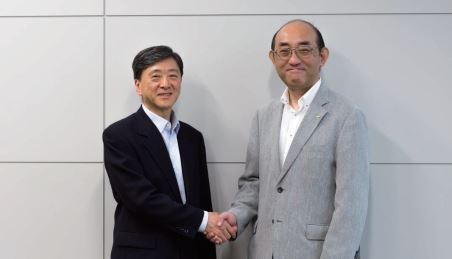
国際エネルギー機関(IEA:International Energy Agency)によると、太陽光エネルギーは、地球上の陸地全てで発電した場合の総量が毎年2万3,000テラワットになります。毎時100万キロワットの原子炉1,000基を365日24時間稼働させて発電するのが1テラワット/年ですから、その2万3,000倍で桁外れに膨大です。全ての陸地を太陽光パネルで埋めることはできませんが、都市とその周辺だけ考えてもすごい量になります。現在、主要なエネルギー源として最も埋蔵量が多いのは石炭です。太陽光発電からは、都市とその周辺での発電だけでもこの石炭の確認埋蔵総量並みのエネルギーを毎年得られます。
日本のエネルギー政策は、戦後、石炭から石油に転換し、ほぼ全量を輸入に頼っています。天然ガスも輸入し、多くを電力に変換して使用しています。石油は港から運ばれ、電力は地方の発電所から供給されるため、石油パイプラインや送電ネットワークが効率良く構築されています。そこに分散型の太陽光発電やバイオマス発電を普及させるには、供給する際の送電ネットワークの付け替えが必要です。森林資源のある地域で木材を燃やし、家畜の糞などを発酵させ、メタンガスを発生させて発電するバイオマス発電の送電ネットワークもありません。これからの社会は、従来型の自動車が電気自動車、水素自動車、燃料電池車に替わるとともに、それらに合わせたエネルギー源を効率良く全国で調達・供給できるような、インフラ整備を進める必要があります。21世紀型エネルギー革命に日本も出遅れないよう早急に取り組むべきです。フランスと英国は2040年までにガソリン自動車の販売を禁止すると発表しています。将来は電気自動車が主軸になるでしょうが、普及が進む過程で新たな動きも出てくるでしょう。すでにフランスなどでは、自動車ディーラーへ行くと電気自動車に無料で充電できる、あるいは街中のパーキングで駐車している間に充電できる、など電気自動車の普及を促す施策も出ていますので、日本も見習う必要があります。
白井:最後に先進国、新興国・途上国の展望についてお聞かせください。先進国はセキュラースタグネーション(長期的停滞)にあり、金利はかつてのような3%、4%という水準ではなく0%近辺が「新常態」(ニューノーマル)という指摘もあります。一方、21世紀に入り資源価格の高騰により資源国を中心に新興国が成長した時期もありましたが、その後資源価格高騰がおさまるとともに経済も停滞気味です。今後モノづくりが新興国・途上国で拡大しても、需要側のパイが限られた状況では供給過剰となり、後発の国が成長できない懸念もあります。2020年から先を展望して、先進国、新興国の経済成長をどのように見ておられますか。
中島:先進国が将来どれだけ成長できるかは、先ほど申し上げたように、国際貿易における新興国とのすみ分け・差別化が一つのカギです。加えて社会システム革新で成長する可能性も考えられます。
スウェーデンは福祉国家として有名ですが、実は成長力も非常に強い国です。「充実した社会保障」と「米国並みの競争社会」という社会システムの両面が成長を支えています。国民は社会保障が充実しているので生活への不安がありません。当然ながら充実した社会保障を維持するには膨大な費用がかかり、国民すなわち最終的には企業の稼ぎがその財源を負担しています。つまりコストがかかる手厚い社会保障の原資を企業収益が支えているのです。優勝劣敗の市場において、雇用の場を提供できない、社会保険料などを払えない企業は存続できませんし、何より国が必要としていません。
国民を支える社会システムとして、政府は教育を通じた人材高度化に力を入れており、教育はもちろん良質な就職先の斡旋まで強力にサポートしています。雇用政策は雇用維持ではなく、より優良な職場を国民に提供する、うまくマッチさせるところに力点があります。
GDP成長率の内訳を見ても分かるように、このような社会システムによって、スウェーデンでは生産性の伸びによる成長が日本より格段に大きくなっています。1人当たりの能力・人材力の高さが生産性を高めています。企業も付加価値によって収益性を高めることに力を入れており、その結果、投資も増えます。人口は増加していませんが、全体で見ると投資や生産性による成長力が米国より高くなっています。
人材強化が国民と国全体の豊かさを実現する枠組みは一つのモデルになるでしょう。もちろん、スウェーデンのような国になることが唯一の道ではありませんが、先進国のニューノーマルは、新興国・途上国のように必ずしも貿易黒字で稼ぐことではありません。サービスなどを充実させて新興国・途上国の求めるものを提供していくことは先進国の役割ですし、そうすることで先進国の生活水準も向上します。
一方、新興国・途上国のあり方を考えますと、資源輸出や安価な労働力の活用ばかりでは立ち行かない国も出てきます。モノの供給が過剰な環境において、どの新興国・途上国も同じパターンで成功するとは限りません。成長を促す経済改革が重要であり、教育水準を上げて人々の資質を高めることが必要です。途上国は産業構造、社会構造自体が収益を効率的に分配できるようになっておらず、成長のひずみによって貧富の差が拡大するケースが多く見られます。
ただ、所得格差拡大は途上国に限った話ではありません。先進国でも米国などでは所得格差が拡大しています。その米国では、同じ企業の中での格差より企業間格差が拡大しています。米国にとどまらず、大企業と中小企業では従業員の平均所得の格差が拡大しており、学歴差による所得格差の拡大も実証されています。一方、日本は特異な国です。戦後の経済成長でも所得格差の拡大はあまりみられませんでした。理由として、私が注目しているのは集団就職です。地方から大量の新卒者が大都市圏に就職し、国民の所得が上がりましたが、その中には中卒で就職した人も多くいました。学歴差による所得格差が図らずも大きくは開かなかったことも一因となって格差拡大を抑える効果を生んだのではないかと考えます。改革によって特定の産業、特定の学歴、特定の地域だけが豊かになる仕組みではなく、うまくリシャッフルしながら国民全体の教育水準を上げていく、全体として国民所得を上げ、その結果不均衡を拡大させない仕組みをつくれると思います。
白井:本日は大変貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました。

今回は、ヒト・モノ・カネ・エネルギーが過剰な時代の到来を訴えておられる、独立行政法人経済産業研究所理事長の中島厚志氏からお話を伺いました。新たな時代において、従来型の成長モデルが国にも企業にも通用しなくなる可能性があり、社会システムの革新と破壊的イノベーションモデルが必要となることは、非常にチャレンジングな課題だと感じました。