研究活動などを通じ構築したネットワークを基に、各分野のリーダーや専門家の方々と対談
コロナ禍の影響を強く受ける変化の時代において、知の創出も盛んなものとなっています。人類はこれまで幾多の危機を乗り越え、知を蓄積してきました。では、人類の知的イノベーションの起源はどこにあるのか。その関心はおのずと「古代ギリシア」に向かいます。現代まで続く「知の体系」の多くが、都市国家アテナイをはじめとする古代ギリシアを端緒にするといわれています。今回は古代ギリシアにおける「哲学の誕生」を研究テーマとされている東京大学の納富信留氏をお招きし、古代ギリシアで学芸・文化が花開いた背景、知的イノベーションを生んだアテナイのありようについて伺い、現在そして未来の、知と都市のあり方について考えていきます。 (聞き手は日立総合計画研究所取締役会長の内藤 理が担当)

東京大学大学院人文社会系研究科 教授
西洋古代哲学専門
1965年東京都生まれ。東京大学文学部第1類哲学専修課程卒業、同大学院 人文科学研究科哲学専攻修士課程修了。1995年英国ケンブリッジ大学大学院古典学部博士号。1998年より九州大学文学部助教授、2008年より慶應義塾大学文学部教授を経て、2016年4月より現職。
哲学および西洋古典学の見地から、古代ギリシアにおける「哲学の誕生」に迫る。国際プラトン学会の会長をはじめ、海外での研究活動を展開。プラトン、ソフィスト思潮における研究は欧文での発表業績もある。近年は、日本における西洋哲学の受容も研究テーマとしている。
著書に、『ソフィストとは誰か?』(人文書院)、『哲学の誕生-ソクラテスとは何者か』(筑摩書房)、『プラトン 理想国の現在』(慶應義塾大学出版会)、『プラトンとの哲学―対話篇をよむ』(岩波書店)、『対話の技法』(笠間書院)、『ギリシア哲学史』(筑摩書房)など多数。
内藤:経営者の中には、今回のテーマとなる古代ギリシアよりも、古代ローマに興味を抱く人が多くいます。紀元前753年に建国され、共和政、帝政と経て、少なくとも1200年間にわたり続いたローマ帝国に、持続可能性の意識を重ねる人も多いのだと思います。
その一方で、西洋文明の先鞭をつけた、言い換えれば「知的イノベーション」が初めに起こった時代・場所を考えると、それは古代ギリシアであり、特にその中心地であるアテナイという都市に着目すべきと考えました。多岐にわたる人財が一時期にアテナイに集結し、現代に至るまで称賛・継承される学術や文化が開花したと伝えられています。
そこで、古代ギリシア、とりわけアテナイでいかに知的イノベーションが起きたかについて、古代ギリシアのみならず世界を俯瞰する視点から、これまで哲学の研究をされてきた納富先生に、幅広く教えをいただきたいと思います。
まず、古代ギリシアが興隆・繁栄した時代は変化に富む特異な時代だったと納富先生もお考えでしょうか。
納富:おっしゃるとおりです。傑出した人物を数多く輩出した点でも、発展した分野が多様にあるという点でも、古代ギリシアの時代は突出しています。その多様さは、近現代のそれをも上回るといってよいのではないでしょうか。
もちろん、古代ギリシアが唯一の存在だったとはいいません。ドイツの哲学者カール・ヤスパースが「枢軸の時代」と表現したように、紀元前500年を中心とする期間に、中国では諸子百家が生まれ、インドでは仏教やジャイナ教が生まれ、そして古代ギリシアでは詩人や哲学者たちが活躍するなど、後世の哲学や宗教の源流が生まれました。しかし、その中でも古代ギリシアの存在は、私自身が研究対象としているからという理由もありますが、やはり得られる示唆が大きいと感じられます。
内藤:フランスの思想家ミシェル・ド・モンテーニュの『エセー』を読むと、3人の「最も傑出した男たち」として、ホメロス、アレクサンドロス大王、そして古代ギリシアの軍人で哲学者でもある、出身地テーバイの勢力拡張に努めたエパメイノンダスという、いずれも古代ギリシアの人物が挙がっています。モンテーニュが、紀元後1〜2世紀に活躍したといわれている古代ローマのギリシア人作家、プルタルコス*1から多大な影響を受けたことはよく知られるところですが、この16世紀のモラリストには、プルタルコス以外にも古代ギリシアの人物たちが魅力的に映っていたのでしょうね。それほど魅力的な人物たちが生まれたのはなぜか。古代ギリシアについて歴史的観点からもう一度、学んでみようという気になりました。

納富:ルネサンス期にも古代ギリシア見直しの機運がありました。モンテーニュに見られるように、「起源としての古代ギリシアを見直す」という機運は、さまざまな時代に見られます。それこそプルタルコスも、さらに古いギリシア古典作品を取り上げて論じていました。モンテーニュの一時代前となるイタリアの思想家マキャベリも『君主論』で古代ギリシアの歴史をひもといているのはよく知られるところです。
古代ギリシアに、歴史の礎となる営みがあり、後世に続く者が伝承してきたこと。
この二つが存在したことが重要ではないでしょうか。ある時ある場所に傑出した人物が出現したとしても、その人物の思想や業績が伝承されなければ、その人物の影響はそこで途絶えてしまいます。
内藤:なるほど。経営学の世界では、イノベーションというのはゼロから何かができるわけではなく、既存知の組み合わせであると聞きます。最近、『戦史』で知られるトゥキディデスの著したことが、地政学のトレンドワードとしてよく語られています。トゥキディデスは、スパルタ対アテナイの争いを「覇権国家対新興国家」といった構図で記述していますが、ハーバード大学のグレアム・アリソン教授が、昨今の米中対立の状況を解説する際に、新興国家が覇権国家に挑むときに戦争が不可避なまでになるジレンマを「トゥキディデスの罠(Thucydides Trap)」と命名したんです。これを聞いて、トゥキディデスはどんな人物だったのか、スパルタ対アテナイの争いはどのような対立だったのかと、皆が知ろうとする。こうして古代ギリシアの人物や業績は伝承されていくのだと思います。
内藤:なぜアテナイで、今日でも称賛され継承されるような学芸・文化が花開いたのかについては、人々の知的交流を促進する「場」の存在が大きいのではないかと思っています。公的な「場」として民会*2、裁判所、劇場などがあり、また私的な「場」として酒宴も執り行われていたと聞きますし、これら「場」の存在が、当時の人々の活気に貢献したのではないかとも思うのですが、いかがお考えですか。
納富:おっしゃったような「場」は、アテナイでは細やかにつくられていました。公的と私的の間になるような「場」もあったようですし、その規模や空間についても、多くの人々が参加する大きなもの、中くらいのもの、小さいものと多様な場が重層的に存在していました。さまざまな形のコミュニケーションを促す「場」が存在していたわけです。「場」があることの意義は、現代社会にも通じると思います。

内藤:そうした「場」で交流する当時の人たちは、例えばホメロスの叙事詩『イリアス』を誰もが読み、内容を体得していたのでしょうか。私は、登場人物の中でも老将ネストールが好きで、作戦会議をするときも空腹ではよい知恵は出ないと食事の支度を提案する場面がありますが、このあたりに老人の知恵を感じるのです。こうした話を、当時のアテナイの人々が共有し、語り合っていたように想像します。
納富:そうですね。誰もが同じことを知っているということに大きな意味がありました。共通のバックグラウンドがあれば、何かを皆で始めるときもゼロから築かずに済むわけですから。誰もがギリシア語を話せて、誰もが同じ神々を信奉している。さらに、オリンピックゲーム、『イリアス』や、『イリアス』と並び称される長編叙事詩『オデュッセイア*3』くらいまで、古代ギリシアの人々にとっての共有財産として考えることができるのではと思います。
しかもアテナイの人たちは、それらの書物を読んでそこから直に教訓を得るというよりも、割と批判的に読んで議論し合っていたようです。現代でいうところの文芸批評のようなイメージでしょうか。例えば、ネストールとオデュッセウスとではどちらの方が賢いかといった議論です。プラトンやアリストテレスの生きた紀元前5〜4世紀ごろには、この手の議論が数多くありました。
やはり「共通のものがある」ことは対話の出発点になりますし、仲間意識の形成につながるものだと思います。時代が下っても、西洋の知識人やリーダーたちは文系・理系を問わず、必ずといってよいほどホメロスやトゥキディデスなどの著書を読んでいました。現代でも、政治家や財界人がプラトンなどから引用するのはごく普通のことです。あたかも、古代ギリシア人が行ってきた知的な「場」の共有を模倣しているかのようです。読んでおいた方がよい、読まなくてもよいという以前に、読まないと「場」に入れないといったことが起こっています。
内藤:経営学の分野で知恵や知識を共有することの重要性を見てみますと、「暗黙知を形式知に変えていく」というプロセスをいかに効率的に行うかが、組織が学習をすべきポイントの一つだといわれています。何もしなければ暗黙知を形式知にはできないので、暗黙知を浮かび上がらせるための「場」が必要となります。
「場」に関連しますと、日立グループでも「NEXPERIENCE*4」という、パートナーとの協創を通じて新しいビジネスやサービスをつくり上げていくための協創方法論があります。そこでは、日立のデザイナーと研究者が培ってきたノウハウを、「手法」「ツール」「空間」として体系化しています。このように交流の仕方を考え、その「場」を設けることで、そこから知恵が出てくるのではないでしょうか。古代ギリシアやアテナイの人たちも議論が好きでしたよね。
納富:とても議論好きでした。交流の活性化には議論好きも一役買っていると思いますが、私たちだったら、むしろ、真剣に議論に付き合うのが大変なくらいです。アテナイの人たちの議論好きは、民族性や文化も関係しているのかもしれません。
内藤:アテナイに人々が集まったのは、都市としての魅力があったからだと思います。とはいえ、当然アテナイにも、そうした繁栄期を迎える前の時代があったわけですよね。
納富:ペルシア戦争より前のアテナイは、さほど国際的な都市ではなかったと理解しています。特に哲学や自然科学に関しては、紀元前10世紀ごろから古代ギリシア人が移住していた、地中海と黒海に囲まれた小アジアのイオニア地方や、南イタリアやシチリアが先端の地であり、アテナイはこれらの分野では未発展でした。
ところが紀元前5世紀になり、アテナイの民主政を確立した改革者クレイステネスが下準備をし、サラミス海戦でペルシア艦隊を破ったアテナイ海軍の創始者テミストクレスや、アテナイの民主政の指導者とされるペリクレスが活躍した時期に、アテナイは繁栄を遂げました。紀元前6世紀が終わり5世紀が始まったころに、そうした大きな変化が見られたのです。もちろんペルシア戦争に勝利したことが繁栄の大きな要因です。ペルシアに最後まで屈服せず、意地を通したことで盟主になったわけです。
未発展だったアテナイですが、1世紀の間に哲学や自然科学が急激に興り、政治や経済の権力も集中しました。しかも、そうした状況をアテナイの市民たちが招来したのです。これらの過程は計画的なものというより、環境が整った結果です。よくできていますね。
内藤:当時のアテナイには、市外から訪れたいわゆる「外国人」が多くいましたね。市民権はないものの、学問や芸術に関わる人が多かった、祭事に参加することもあったとも聞きます。一定の影響力があったのではないでしょうか。
納富:そのとおりです。知識人たちが外からアテナイに集まり、アテナイの土着文化とうまい具合にマッチしました。多様なバックグラウンドを持つ人たちが、紀元前5世紀にアテナイという都市で交じり合ったわけです。
悲劇や喜劇の詩人はアテナイ出身者が多かった一方で、自然科学系の知識人は基本的にアテナイの外から来た人たちでした。ソフィスト(職業的教育者)たちもそうです。哲学の分野では、ソクラテスが実質的に最初のアテナイ人哲学者です。
どうして外から知識人たちがアテナイにやって来たかというと、経済的需要があったからです。アテナイの人々が市民教育のために「授業料を払うから自然科学や弁論術を教えてほしい」と希求し、それに応じたわけです。紀元前5世紀のアテナイで活躍した知識人の大半は「外国人」たちでした。ただしそれらの人々は定住するでもなく、客人として滞在しつつ、文化に多大な影響を与えていたことになります。
内藤:アテナイに多様な人財がやってくる都市的な要因もあったのでしょうか。
納富:アテナイを含め、各ポリスとも小規模だったので、自分たちのポリスだけでは経済や文化が完結しなかったという事情はあったのでしょう。それにより、古代ギリシアで人々の流動性が高まったのは間違いありません。
とはいえ、紀元前5世紀、顕著に人々がアテナイへと向かい、集い、そして動きまわっていたわけで、それまでとだいぶ異なる状況だったとは思います。一方、アテナイ市民はというと、そうした流動性を上手に利用し、開かれた「場」をつくることで自分たちの政治や教育や文化を活性化させたという側面があります。
内藤:プラトンの対話篇『プロタゴラス』を読むと、ソクラテスが友人に、ソフィストの祖とされるプロタゴラスがアテナイに来ていることを知らせて、友人が驚く場面がありますね。読み進めると、ソクラテスはプロタゴラスに一定の敬意を払っていて、一問一答で相手を突き詰めるのとは別のソクラテスの姿が見られて新鮮でした。
納富:『プロタゴラス』篇の冒頭は、まさに紀元前5世紀後半の状況を象徴する代表的な場面といえます。若者が興奮しながらソクラテスのところに来て、プロタゴラスがアテナイに来ているなら、彼に教えを請いたいといっています。若者は知識人に会うという知的興奮を抱いていたわけです。このように、知への渇望をアテナイの人たちは持っていました。
内藤:知的イノベーションが発現する都市とはどういうものか。その都市のあり方を考えるとき、現代においては「デジタル技術の進展」という要素を加味する必要があります。COVID-19の拡大が、人と人が直接に会うという従来のコミュニケーション方法にも変容をもたらしている昨今であればなおのことです。
納富:昨今では、デジタル技術を用いた対話の可能性や拡張性を感じますね。
大学の講義も昨年度はほぼオンライン形式になりました。その中で、視線や息遣い、あうんの呼吸のような、肉体が持っているコミュニケーション手段の不在に違和感を覚えることがあります。みなさんも経験があるかもしれませんが、画面に映っている相手の目に自分の視線を合わせると、自分のカメラは少しずれた位置にあるため、相手には伏し目がちに見えてしまうことがあります。
一方で、コンピュータやアプリなどのツールさえ持っていれば、これまでコミュニケーションに参加していなかった人たちが対話や議論に加われるようになります。社会的格差の問題解消にもつながり得るものだと思います。これまでできなかったことをデジタル技術で実現していく。そこでは新たな発見もあり、課題も浮かび上がる。ある意味、壮大な社会実験をしているとも捉えられます。今後、遠隔のコミュニケーションが増えるに従って、そこに体があること・ないことと、コミュニケーションを取ることの関係性が、より考察されていくでしょう。
内藤:納富先生は、離れたところにいる学生たちと、デジタル技術でコミュニケーションを取っていらっしゃいます。それだけでなく、2000年も前にアテナイに生きていた人物たちとも、知識と想像力を駆使してコミュニケーションを取っていらっしゃいますよね。
アテナイという活気のある都市を考えるとき、私は愛媛県松山市の取り組みが思い浮かびました。日立東大ラボ*5が進める「ハビタット・イノベーション*6」プロジェクトの実装フィールドの一つです。人々の行動データとデジタル技術を活用した社会課題の解決とQOL向上をめざし、スマートシティ実現に向けた実証に取り組んでいます。見上げると存在する松山城が、あたかもアテナイのアクロポリスに建立されたパルテノン神殿を想起させるというわけではないですが。納富先生もアテナイに行かれたときは、当時の街や人たちに思いを馳せるのではないですか。
納富:そうですね。想像力をたくましくしてアテナイの街を巡ります。すると、むしろ現在は「何もない」ということに感動を覚えます。かつてプラトンが、紀元前387年ごろに開いた学園アカデメイア*7があった場所も、今は住宅街にある普通の公園になっています。最初に訪れたのは学生時代でした。プラトンたちが議論をしていたまさにその地で、研究仲間たちと議論を交わしました。想像力が膨らんで感動しました。

内藤:土地の記憶のようなものはきっとあるのでしょうね。
納富:確かにあります。アカデメイアはもともとアカデーモスという神を祭る神域でした。そのためか今もその跡地はアパート群などと一線を画し、森になっています。日本でいえば、神社の境内のようなものです。生活空間の喧騒から離れて、精神を落ち着かせて議論をするのにはふさわしい場所です。
内藤:私たちも中央研究所内に開設した研究開発拠点を「協創の森*8」と呼んでいます。武蔵野に育つ約3万本の原生林といった自然を可能な限り残し、その豊かな自然環境を感じながら研究開発できる環境づくりをしています。日立グループにとってのアカデメイアのような場所です。
納富:人間にとって、森や、緑のある環境というのは大事なものですね。
内藤:アテナイのような知的な刺激に満ちた都市のあり方を考えると、やはり「人間中心」という考えが前提としてあるのではないでしょうか。先ほど申し上げた、日立東大ラボにおけるデータ駆動型スマートシティの実現においても「人間中心」の社会の実現を指針としています。人と人が考え、語り合う都市は基本的ににぎわうものであり、都市はにぎわってこそ命が与えられるという感覚もあります。そして「人間中心」を前提としつつ、そこに新しい知恵や技術を吹き込むことで「人間中心」をより際立たせることができるのではないかと考えています。
納富:新しい知恵や技術がどのように生まれ、生かされるかは考えさせられる問いです。反面、二千数百年前の社会を対象にして研究し続けていると、「新しさ」を追求した結果として、新しいものが生まれるのではないような気がします。新しさそれ自体には、価値はありません。そのため、新しいことを追求していくというのは、いささか本末転倒という感を抱いてしまいます。なぜなら「新しさ」は、つくろうとしてできるものではないからです。学生たちの論文を見ていても、目新しさだけに主眼を置いたものは、細部にこだわるような話に陥りがちで、論文全体としてはさほど秀でたものにはなりません。
それでは新しい知恵や技術が生まれる際の本質的な要素とはどのようなものか。私は、きちんと考えている人がきちんとしたことに取り組むと、必然的にそこに新しい知恵や技術が伴われると思うのです。きちんとしたことというのは「王道」と言い換えてもよいでしょう。王道を歩んでいると、そこから新しいものが生まれてくるのではないでしょうか。
現代を生きる私たちが「これは新しい」と感じるものでも、実は2000年以上前の古代ギリシアや中国で同様のことがあったという話はよくあります。過去にも行われていたものは、新しいとはいえません。しかし、現代において再び王道を行くことが、衝撃的な影響をもたらすということはあり得ると思います。
大学の研究活動でも、文系・理系問わずイノベーションにつながる知は生まれます。それらの多くは「イノベーションを起こすために研究した」といった自己目的からではありません。研究者が「これは本質的に重要だ」と考えた基礎研究の中からイノベーションの萌芽を得られることの方が多い。これがふさわしいあり方ではないかと思っています。
内藤:今回納富先生にお会いしてぜひとも伺いたかったのが、「無知の知」と「不知の自覚」についてです。ソクラテスの標語として知られている「無知の知」という言葉の解釈には誤解があり、これを「不知の自覚」に改めるべきだと先生は述べていらっしゃいます*9。
納富:この問題について取り上げていただくのはありがたいことです。私自身の中ではやはり、ソクラテスが「無知の知」を語ったという流布した見方は、根本的な誤解であったと考えています。「無知の知」という言葉は、人々を分かったつもりにさせるものの、実は意味の分からないものです。しかも、おっしゃっていただいたように、ソクラテスの言葉を伝えているプラトンは、ソクラテスが「無知の知」に相当する話をしたとは、何一つ述べていません。
「無知の知」という言葉が日本でこれほどまで広まっているのは、多くの方がソクラテスについて知識や関心を持っていることの現れであるともいえます。ソクラテスは明治時代すでに高い人気がありました。それゆえ、その後デフォルメが生じて、「『無知の知』を語った」という誤った解釈になってしまったのです。
ソクラテスの考え方に人気があるのはよいことだ、と認めたい部分もあります。しかし、語っていないことが、誤った形で広まってしまっている状況は、少しでも直していかなければなりません。
内藤:高校時代、私の仲間は「『無知の知』というけれど、意味がよく分からない。知らないのに知っているとはどういう意味だ」やら「それって、知らないと思っているだけなんじゃないの」などといっていました。こうした疑問を倫理の先生に投げかけてみると、「君たちの疑問はもっともだ。ぜひ大学で勉強しなさい。けれども、『無知の知』は受験に出るから覚えておかないと、大学には行けないよ」といっておられました。
納富:そういうことがおありでしたか。最近はようやく高校の教科書でも「無知の知」と「不知の自覚」の併記が見られたり、「従来は『無知の知』と呼ばれていた」といった注釈的記述が見られたりするので、半歩前進というところでしょうか。
内藤:哲学も哲学史も、言葉をとても大切にする学問でしょうから、先生のご苦労をお察しします。
内藤:納富先生は筑摩書房から2020年に刊行された『世界哲学史』全9巻シリーズで責任編集のお一人となり編纂 を担われました。私も順番に楽しみ、味わわせていただいているところです。
読んでいて重要だと思ったのは、先生が第1巻の序章で書かれていた「世界哲学とは、哲学において世界を問い、世界という視野から哲学そのものを問い直す試み」というお考えです。西洋哲学と東洋哲学といった単純な切り分けでなく世界全体という文脈において、また通時的ではなく共時的に思考構造を比較することで、哲学を見つめ直そうとしておられることが伝わってきます。
納富:私の中では「試み」というのがふさわしい表現です。
このシリーズは、第8巻までと「未来をひらく」をテーマにした別巻の全9巻からなりますが、一つのグローバルな視点から、全てのことが見えるといったつくりにはなっていません。巻によって構成もさまざまで、ぎくしゃくとした印象があるかもしれません。しかし、そこに面白さがあります。同じ時代なのにこのように多様な考え方があると、読み始めれば見えてくるものがあるはずです。
同時に「こういう見方で、このように捉えてほしい」といったメッセージを、私を含め編者たちは持っていません。私たちが集めてきた材料をどさっと置いて、あとは読者の方に、どういう角度からどう見るかは委ねる。東洋のことが好きな読者が見た世界と、哲学は西洋にしかないと思っている人が見る世界は違って映るでしょう。
哲学の営みでは、各時代や各地域で素晴らしいことが起きているものです。それらを拾い上げていく作業が必要ではないかと考えていました。私たちは「世界哲学」を英語で“World Philosophy”と表現しました。“Global Philosophy”ではありません。画一的に哲学を見るのでなく、これまで拾われなかったような哲学も一つ一つ見ていきたいという意味を込めています。そうすることで、私たちの予想を超えて、多様なものが見えてくるのではないかと考えています。
内藤:一つの視点だけで物事を決め付けたように捉えると、反対側が見えなくなったり、真の理解を失したりしてしまう恐れはあります。日本を離れて海外に行けば、そこでの世界地図の真ん中にはその国が置かれています。“Think Globally, Act Locally”ともよくいわれますが、少なくとも視点を固定化しないことは重要だと思います。
納富:世界哲学は、一つの視点ではなくて、多様な視点で、しかもその視点をずらしたり、複合させたりもして、見ることが重要なんだと思います。
欧米や中国など、世界の研究者たちと協力して世界哲学に取り組んでいます。その一方で、私の感触でいうと、日本は世界哲学に取り組むのに最も向いている場所でもあるのです。
内藤:そうなのですか。それはなぜでしょう。
納富:日本には、不思議なほどの「バランスのよさ」があるからです。インドや中国の哲学の要素を持ちながら、西洋哲学も取り入れている。しかも、西洋哲学も英語圏のものだけでなく、フランス語圏、ドイツ語圏、場合によってはロシア語圏の哲学も含まれます。もちろん、日本土着の哲学的な要素もあります。このようなバランスが保たれている国は、世界において日本しかありません。
内藤:そうですか。日本の役割に対する期待感が持てる、とても価値がある試みであることが理解できます。
納富:バランスが取れていて、自分を押し付けるようなこともせず、さまざまなところに気配りできる。これは日本人の特徴ではないかとも思います。哲学以外の分野でも、こうしたポジションを意識することは重要ではないでしょうか。
内藤:ますます『世界哲学史』シリーズを読み進めるのが楽しみになってきました。
内藤:私たちのシンクタンク活動に、哲学あるいは西洋古典の視点からぜひアドバイスをいただけますでしょうか。
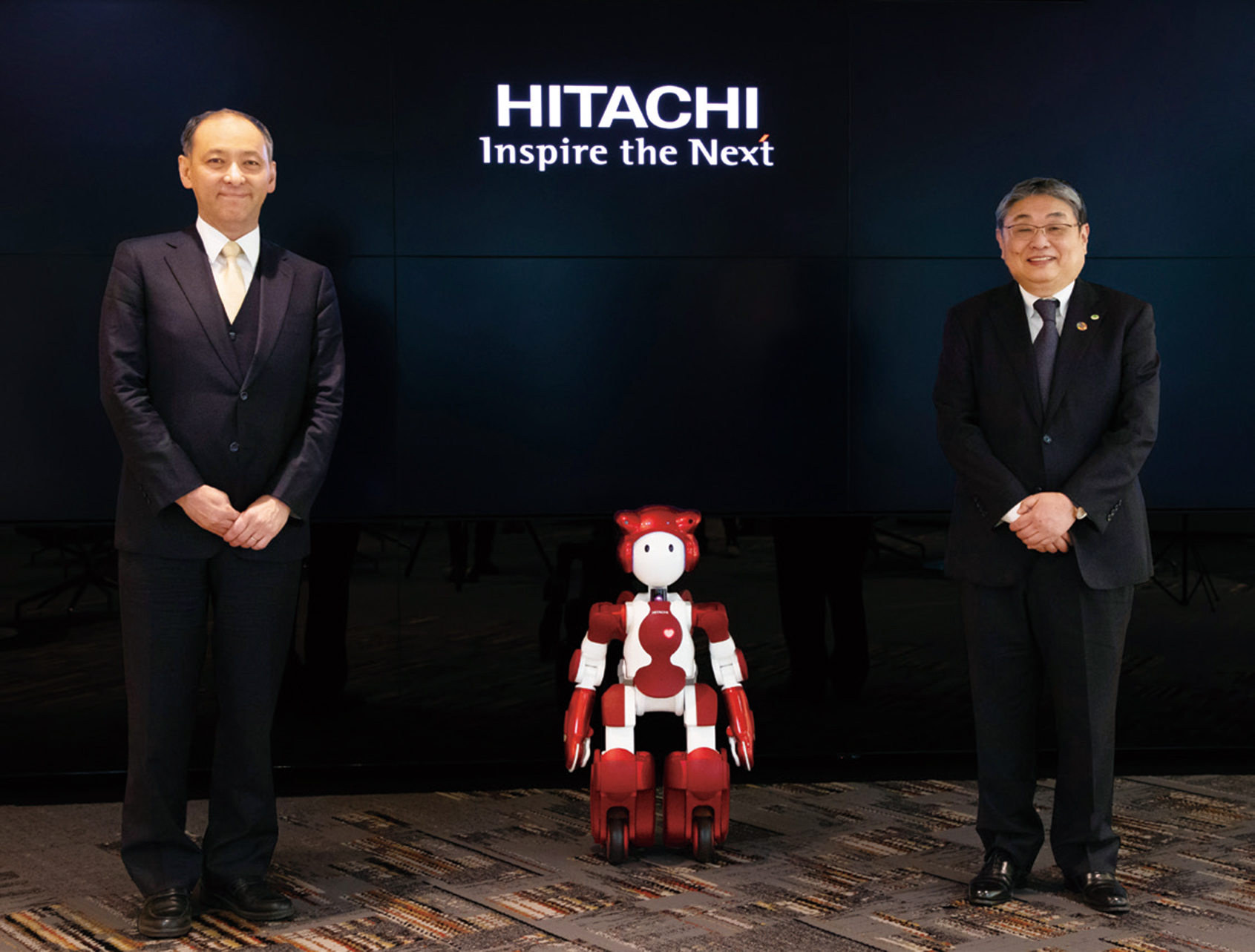
納富:あまり大それたことはいえないのですが、それでは「普遍」という概念がギリシア哲学から始まったということについてお話させていただきます。
内藤:「普遍」ですか。古代ギリシアの古典作品には、なぜ時代や国を超越し、世界の人々に広く受容されるような普遍性があるのかと疑問を抱いてきましたが、そもそも普遍の概念が古代ギリシアから出たというのは面白いですね。
納富:古代ギリシア以来、私たちは日常的に「普遍」という言葉を使っています。英語の“Universal”という広く知られた単語です。この言葉は、もとはアリストテレスが造語したのです。彼は“καθολου”と呼びました。
この言葉の意味は、「全てのものに当てはまる」といったものです。しかし、単純に全てに当てはまるというだけではありません。「本質的に当てはまる」ことが、「普遍」には重要です。どんな場でも時代や人にでも当てはまる真理、それが「普遍的」ということなのです。
ですが、第二次世界大戦後のポストモダニズムと呼ばれる時代において、普遍性を否定する人々が出てきました。普遍性を重視している人たちは結局のところ他人に自分の考えを押し付けているにすぎないと考えたわけです。そして普遍主義に代わって、相対主義や多元主義の考えが強まってきました。
ところが21世紀になり、中でもここ5年ほどは、普遍性の概念が哲学においては復権してきているのです。「普遍」という語を書名に用いた哲学書もここ数年、出てきています。
内藤:それはどのような要因によるものでしょうか。
納富:一昔前は、普遍性を重視すれば人類は全体として繁栄し幸せになるかというと、どうもそうではないという反省や批判の風潮がありました。しかし現在は、やはり普遍性、真実や真理が哲学の基礎にあり、これらを再考すべきではないかという考え方が出てきています。普遍性とはどのような意味であるのかを、もっと真剣に追究しようという意味です。いわば揺り戻しのような現象が起きていると捉えています。
現代において、経済を見ても政治を見ても、中国には中国の、米国には米国の論理があります。どの論理が勝っているのか勝負をしようということでなく、共通の目標に向かっていこうとするとき、どこかで普遍性を確保しなければなりません。
企業活動において「普遍性について考えましょう」といっても、なかなかそうはいかないかもしれません。しかし、普遍というものを自明のものと捉えるのでなく、「普遍性を持つにはどうすればよいのか」という問題を考え、普遍的に世界をみていく視野と態度を養っていくべき時代にさしかかっているのは確かなことです。
改めて、意味を探究すべきキーワードとして「普遍」を捉えておかれるとよいのではないでしょうか。
内藤:今、日立は、社会イノベーションを通じて「社会価値」「環境価値」「経済価値」を創出することをめざしています。経済価値は客観的に数値化できますが、社会価値などは、数値化が困難です。こうした価値を考えるには、普遍的なものを改めて考えてみることが次の世代につなげるうえでも大切かもしれないですね。
大切なキーワードとメッセージをご教示いただきました。本日はどうもありがとうございました。
※今回の対談は、フィジカルディスタンスを保って実施しました。

医学の祖ヒポクラテスは「人生は短いが芸術は長い」“ὁ βίος βραχύς,ἡδὲ τέχνη μακρή.” という言葉を残しました。元のギリシア語のテクネ―は技術、技能という意味であり、ヒポクラテスゆえにこれは医学的技能を指す、すなわち人の一生は短いが医学によって発見された技能は長く人々を救うのだから心して励めよ、という意味でしたが、後に芸術と解されています。コロナ禍の今、東京大学の納富教授のお話を通じ、古代ギリシアの賢人たちに、イノベーション発現プロセスや知的スマートシティなどのヒントを教えられた気がします。われわれも「長く」残る価値を生み出したいものです。
株式会社日立総合計画研究所 取締役会長 内藤理