研究活動などを通じ構築したネットワークを基に、各分野のリーダーや専門家の方々と対談
人工知能(AI)と共に次世代の知を担うツールとして期待される量子コンピュータは、世界的に激しい開発競争が繰り広げられています。今回は日本の量子コンピュータ研究の先駆けとして知られる物理学者の伊藤公平氏をお招きし、量子コンピュータ開発における現状と展望を伺いました。社会実装をめざす開発段階においては、一つの企業だけで進めることは困難であり、複数の企業、大学間で連携する取り組みが進められています。産学を挙げた協調と競争の在り方と、その実行に際して重要となる人材の多様性について考えます。(聞き手は、日立総合計画研究所取締役会長の北山 隆一が担当)

慶應義塾長
1965年兵庫県生まれ。博士(材料科学)。1989年慶應義塾大学理工学部計測工学科を卒業。カリフォルニア大学バークレー校にて修士号(1992年)・博士号(1994年)取得。1995年慶應義塾大学理工学部助手。専任講師、助教授を経て、2007年より教授。2017年より慶應義塾大学理工学部長・理工学研究科委員長、2021年より現職。
専門は固体物理、量子コンピュータ、電子材料、ナノテクノロジー、半導体同位体工学。東京大学特任教授、国立情報学研究所客員教授、東京大学客員教授、日本物理学会理事、応用物理学会理事、科学技術振興機構さきがけ研究領域「量子の状態制御と機能化」領域総括、文部科学省 Q-LEAP 量子コンピュータ分野・プログラムディレクターなどを歴任。2020年より日本学術会議会員。
2006年日本IBM科学賞、2009年日本学術振興会賞を受賞。2015年応用物理学会フェロー表彰、2021年米国物理学会フェロー表彰。共著に『カーボンが創る未来社会』(丸善プラネット)『Silicon Quantum Information Processing』(Springer)、『物性物理学ハンドブック』(朝倉書店)、『基礎からの量子光学』(オプトロニクス社)など多数
北山:量子コンピュータは、古典的なコンピュータでは膨大な時間がかかるシミュレーションや複雑な組み合わせの最適化などに適していますが、選択肢が絞られた中での最適解の計算はむしろ古典的なコンピュータの方が適しているともいわれます。古典的なコンピュータと比較したときの量子コンピュータの長所と短所、期待される分野について教えていただけますか。

伊藤:量子コンピュータの最大の特徴は、一つのビットを、0でもあり1でもあるという状態で使えることです。例えば「ボトルの中に赤ワインと白ワインが半分の確率で入っている」という場合、100本のボトルがあれば、赤と白が50本ずつあるはず、というのが普通の考え方ですが、「1本のボトルが赤でもあり、白でもある」と考えるのが量子コンピュータです。そのボトルを開けるまではどちらであるかは決まらず、開けた瞬間に赤か白かが決まる、その確率が50%なのです。この状態があることを認めなければ話は終わってしまうのですが、量子力学的にはそれが可能です。例えばウラン238に中性子が1個付くと不安定なウラン239になります。このウラン239は徐々にプルトニウム239に変わります。100個のウラン239のうち、50個がプルトニウム239に変わるまでの時間を半減期といいますが、1個のウラン239に注目したとき、それは半減期に50%の確率でウランでもありプルトニウムでもある、というのが量子力学的な重ね合わせの考え方です。この考え方が使えれば、一つのビットは0と1の二つの状態、二つになったときは、0・0、0・1、1・0、1・1の4種類の状態が持てます。三つではさらに2倍の8種類、4ビットでは16種類と、ビットの数だけ2を掛けた数の種類が持てるのです。ビットが280個あると、つまり2を280回掛けると、宇宙にある原子の数と同じになりますので、0から宇宙にある原子の数までの連続的な数字を全て一緒に持つことができる。これを使って計算すると、最初に0を試して次に1を試して、次に2を試して、3を試してとすることなく、全ての数を同時並行的に進める超並列計算ができるのです。けれども、ものすごい種類の数を持っているにもかかわらず、最後に読み出すときはそのうちの1種類しか読めないのです。ビットが3個の例でいえば、0・0・0から1・1・1までの8種類の数字を同時に持っているにもかかわらず、最後に読み出すときは0・0・1もしくは1・0・0など一つしか読み出せないのです。量子計算のいちばん難しいところはそこにあります。超並列計算をしながらも、最後にたった一つの集約した状態で答えが得られる、そういう問題に向いているのです。逆にいえば、そのような問題が世の中にどれだけあるのかが、量子コンピュータの開発者にとっていちばん大きな問いなのです。現在の暗号技術の基となっている素因数分解は、量子コンピュータが解決できる問題の典型例です。1994年にピーター・ショアがこの問題を解くための計算方法であるショアのアルゴリズムを発見しました。これによって量子コンピュータは使い物になることが分かり、量子コンピュータを作る機運が一気に高まりました。とはいうものの、この問題しか解けないのでは、実用的ではありません。これ以外に、量子コンピュータが解ける問題をどれだけ見つけられるかが、非常に重要になります。その問題を探すのが量子コンピュータのアルゴリズムとソフトウエア研究であり、その計算を実行する舞台を作るのがハードウエア研究です。それら両方の研究が進展して、現実に本物の量子コンピュータができましたが、できることはまだ限られています。世の中のどのような問題が解けるのか、どのような問題が産業分野に適用可能なのか、今はそれを明らかにするステージです。
北山:世の中で量子コンピュータに適した問題や適用分野を明確にするためにも社会実装は重要なのですね。世界を見渡すと、量子コンピュータの研究開発から社会実装に至るまで、IBMやGoogleなど海外の巨大ITベンダーが巨額の投資をしており、特に米国が進んでいるとの印象を持っています。量子コンピュータにおける日本の位置付けは世界的に見てどのようなものでしょうか。今後日本はどのような取り組みをしていくべきでしょうか。
伊藤:1970年代後半から80年代にかけて日本の半導体技術が世界を席巻したころ、日本はベル研究所をはじめとする米国や欧州の研究機関が発見した熱酸化などの技術を改善しただけだ、といわれました。そして、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』*1話題になったときも、「日本人は創造性に欠けている。ノーベル賞受賞者はどれだけ出るのか」といわれました。その後バブルが崩壊すると、技術力で日本を復活させなければという機運が高まり、科学技術基本法が制定され、95年ごろからは大学にも高額な研究予算が付くようになりました。それによって日本が世界に誇る量子コンピュータ技術が生まれたのです。98年には西森秀稔東京工業大学教授により、量子アニーリングの基礎理論の発表という重要な基礎研究の成果が出ました。また99年に開発された世界初の超電導量子ビットは、NECの基礎研究所の成果でした。私もその恩恵を受けて、シリコン量子ビットの開発に取り組むことができました。ところが、残念ながらそれらは製品化に向けた活動にうまくつながらなかったのです。
私が逆に知りたいのは、IBMやGoogle、その他のスタートアップ企業が量子コンピュータに巨額の投資をしている過程を、かつて半導体技術であれだけの実績を築き上げてきた日本企業がどのように見ているのかということです。私のような基礎研究者から見ると、台湾のTSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)が2025年をめどに計画している2ナノ対応の高性能半導体工場を、日本企業が造ることが技術的に可能なら、今後日本企業が量子コンピュータを作るのも、もっと簡単にできるはずだと考えます。

北山:まず、半導体技術の現状を述べますと、日本の半導体生産を軌道に乗せるためには半導体の性能を上げていく必要があると考えます。他社のお考えやお取り組みについてコメントはできませんが、日立の場合、いったん手放してしまった半導体技術をもう一度取り戻すよりも、質の高い半導体製品を高い生産性で製造するプロセスに貢献する方が早くお役に立てるということです。幸い日立には高精度の測定技術を活用した検査装置類を持っているので、既にお役に立ち始めていると思っております。
伊藤:コンソーシアムという一つのチームに参加するということですね。日立は、他ではまねのできないワン・アンド・オンリーの技術をいろいろお持ちですね。
北山:半導体メーカーにとって欠かせない技術を持っていることは確かです。特にスタートアップ時には、国・政府も含めていろいろな企業の協力・連携がなければ立ち上がりません。1社で全てをやるのではなく、それぞれ得意な分野を持つ企業が力を出し合いながら進めていくことが必要だと考えます。それは量子コンピュータ分野においても同じでしょうか。
伊藤:そうですね。そういう意味ではQ-STAR*2の中で上手にベストチームを組むことができれば量子コンピュータ技術の完成度が非常に高くなると思います。
北山:今が第3次ブームにあるといわれているAIは、1950年代の研究着手から何度かブームが訪れたものの、世の中の期待に対して技術の進歩が追い付いてこなかったと指摘されることがあります。リチャード・P・ファインマンが1981年に量子コンピュータの概念に触れてから約40年がたち、量子コンピュータに対しこれまでにない期待が高まっていますが、その期待に対して技術が応えていくためには、何をすればよいでしょうか。
伊藤:AIは、コンピュータとディープラーニングそれぞれの技術的発展により大きなブレークスルーがあり、実際に使える物になりました。量子コンピュータで考えると、まずハードウエア面では、単に超電導量子ビットチップを用意すればよいわけではなく、ワイヤリング、マイクロ波発生装置、磁石の材料など、いろいろなものが必要です。冷却装置も重要ですし、日本が得意とする計測技術を含めてさまざまな技術の集積が必要になります。これらが全て一緒にならなければ、大きなブレークスルーは起きません。おそらくIBMも、自社で全てを開発するのではなくて、ある程度自分たちのシステムをオープンにしながら、各種部品・技術一つ一つのニーズを他者に理解してもらえる環境を整え、それによってチームとして研究を発展させようと考えていると思います。次にソフトウエア面では、アルゴリズムを作る応用数学展開力と、それをコンピュータのプログラムに落とし込むコンピュータサイエンス力の二つが必要です。それらに加えて、より大切なのは、量子コンピュータに解かせる問題の選択です。どの問題に挑戦するべきか、ここに産業界の方々に加わっていただきたいと考えています。「うちの会社ではこういう問題に時間がかかり過ぎて困っている」、「こういう問題が解けなくて困っている」、そのような実例がたくさん集まってくれば、「この問題ならば今のコンピュータの能力をしのぐことができるのではないか」という見通しが立ち、量子計算用のアルゴリズム開発、ソフトウエア開発につながるのです。例えばIBMは、量子コンピュータを発表して6~7年たちますが、これまでの間ソフトウエア開発を進めることによって、装置の性能をどんどん伸ばしています。その伸び率はムーアの法則*3に匹敵するもので、2045年には量子コンピュータが現在のコンピュータの性能を上回ると予測されています。さらに、全てを量子コンピュータに計算させるのではなく、現在のスーパーコンピュータとAIを併用しつつ、鍵となる部分にのみ量子コンピュータを使うことができれば、2030年には現在のコンピュータの性能を超えるともいわれています。そのために必要となるのは、結局のところ総合力です。量子の研究者が量子コンピュータの開発だけに集中していても、問題を見つけることはできません。最終的な目標は量子コンピュータを作ることではなくて、コンピュータの性能を上げ、現在のコンピュータの発展をスピードアップすることなのです。

北山:IBMやGoogleは、全方位的にというよりも、自動車業界や化学業界と密に協力し、その分野に特化して開発を進めているようにも見えます。他の業界でも量子コンピュータに解かせる問題の議論は進んでいるのでしょうか。
伊藤:Googleは自分たちで半導体チップもデザインしていますし、実際に作っていますから、量子コンピュータに関する相当な知識をチームとして持っていることは間違いありません。IBMもそうです。ただ、特定の企業や業界に特化してしまうと、問題は限定されてしまいます。自動車企業は自動車の問題しか持ってこないし、化学企業は化学の問題しか持ってきません。慶應義塾大学の量子コンピューティングセンターは、日立製作所をはじめ、金融業界では三菱UFJフィナンシャル・グループ、みずほフィナンシャルグループ、三井住友信託銀行の3社、化学業界はJSRと三菱ケミカルの2社、そしてソニーグループとトヨタ自動車の、計8社に参加していただいています。各社のトップ研究者が慶應に集まり、それぞれの企業・業界が抱えている問題を持ち寄って研究を進めています。例えば「ある金融商品の価格を決める計算に8時間もかかる」という金融業界の問題について、他の業界の人が加わると、さまざまな角度から質疑がなされ、議論を深めることができます。このケースでは、計算結果の精度を上げたいがために、あらゆる可能性を考慮した上で平均を取っていることが、計算に時間を要している原因であることが明らかになり、それに対して「重ね合わせで一気に計算できる」という解決策が出されました。取り上げたケースは金融業界の問題であっても、解決策はモンテカルロシミュレーションという数学の手法ですから、化学業界でも使えますし、業界を超えて協力して研究することができるのです。この問題については、すでにみずほフィナンシャルグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループ、慶應義塾大学、IBMの4者の共著論文が出ています。二つの金融グループが共著で論文を出したのは初めてだそうです。今後もこのような論文がどんどん出てくると確信しています。また先日は、二つの企業の株価の変化に相関があるかどうかを調べた論文が発表されました。例えば自動車業界では、トヨタ、スバル、日産などの株価に相関があるだろうことは想像がつきますが、全く違う業界に属する企業のペアについて同調や相反の動きを探し出すためには、多くの組み合わせを見ることになり、そのような膨大な計算は今のコンピュータではできません。しかし、「これは量子コンピュータならできそうだ」ということが見えてきたのです。計算方法を開発し、2008年のリーマンショック発生当時の株式市場データで計算してみたところ、実際に相関を示す企業株価の組み合わせを見つけることができました。性能的にはまだ今のコンピュータには及ばないのですが、計算パワーを考えれば、いずれ量子コンピュータが上回ることになると思います。このペアの相関は、実は多くの分野の基礎研究にもつながります。例えば製薬業界においては、さまざまなバイオマーカーの相関を明らかにすることによって、薬効や副作用予測の精度を高めることもできるでしょう。現実的な一つ一つの問題の奥に非常に大きな広がりがあるということを強く感じます。量子コンピュータが、いつ今のコンピュータに勝てるようになるか。これは大事な論点ですが、計算機科学として証明するのが非常に難しいのです。あらゆる利用シーンを想定してメモリサイズをどう見積もるかなど、いろいろなことが関わってきますし、ステップ数だけでなく同時にクロックスピードも考えなければならないため、厳密に論文にするのは難しい。とはいえ、最終的に大切なのは、企業の方々が自社の問題をいくつか試してみて、具体的な使い方の中で、ここは量子コンピュータの方がいいと分かることなのだと思います。それが感覚として分かったときに、その問題に対しては量子コンピュータの方が優れているといえますから。そうなる日をめざすのが私たちのコンソーシアムの目的であり、おそらくはQ-STARの目的でもあるのだろうと思います。
北山:企業間連携では、オープンな研究開発が理想ではあるものの、それぞれのライバル企業には渡したくない情報もあります。こうした協調領域と競争領域の線引きをどのようにしていくべきか、現時点では手付かずの状況のように思います。先ほどお話を伺った共著論文が出されるような段階ではオープン化が進んでいると思うのですが、その次の段階、社会実装を含め実用化に落とし込んでいくときに、それをどこまで維持できるかは重要な課題です。これをブレークスルーしていくことで、量子コンピュータの社会実装のスピードが大きく変わるのではないでしょうか。
伊藤:企業の方々がオープンな研究開発を続けたいとお考えになること自体、大変な変革だと感じていますし、そのマインドセットがありながら「ここはオープンにできない」と各企業が思うようなレベルにまで量子コンピュータの開発が進んだら、それこそすごいことだと思います。良い意味で競争の段階に入るわけです。光ファイバー技術を例にとると、各社がお互いに国際標準や材料・技術特許に関してしのぎを削っていますが、これは産業化がかなり進んだ証しでもあります。私は24年間、シリコン量子コンピュータの研究開発に携わってきました。かつて多くの研究者が「そんなことはできるはずがない」と思う中、日立は日立ケンブリッジラボ*4の枠組みの中で、私はドイツ、英国、カナダ、オーストラリアなどの海外パートナーを増やしながら先端技術を切り開いてきた結果、多くの人が考え付かなかった技術レベルを達成し、本物の量子コンピュータが完成しました。
最初に量子コンピュータのプログラミングをしたときは、手が震えるほどでした。作ろうとしてきた本人でありながら、本当にこんな日が来るとは思っていなかったのです。改めてこの日が来たのだと実感すると同時に、これからは量子コンピュータを使うためのアルゴリズムやソフトウエアを作らなければ、ハードウエアを作った意味がないと思ったのです。そのためには基礎的な数学力が必要不可欠です。大学で最先端クラスの知見を持つ数学者の協力を得ながら、新しいアルゴリズムやソフトウエアを開発していくことが、応用段階での産学協創の理想像だと思います。その際、今後は大学の貢献が徐々に減っていくと思います。コンソーシアムの形から、競争の段階に持っていくまでが大学の役目ですよね。今は、シリコン量子コンピュータが2量子ビットを実現し、3量子ビットが作れるかどうかという段階ですが、それ以上の集積化はもう大学の仕事ではありません。物理的な基本を全て示した後は、完全に企業に受け渡す段階だと考えます。われわれ大学側が常に先を見て、受け渡しの段階まで共同研究の場を作っていく、次にQ-STARのような企業連合が、それぞれの協調領域で開発に取り組む。そのうちに競争領域が増えていくのだろうと思うのです。企業の皆さんがオープンイノベーションの協調領域から競争領域へと移行したと感じられたら、それは大成功だと私は思います。
北山:狭い日本で同じ業界に多くの企業がひしめき合って競争している状況ですので、オープンイノベーションは政府の力を借りながらでも進めていく必要があると思いますが、一方でそれは政局によって大きく左右されます。量子コンピュータの研究開発を取り巻く環境も、米中の技術覇権争いの激化やロシアのウクライナ侵攻による経済制裁など、地政学的な問題に巻き込まれ、オープンイノベーションに対する壁のようなものが出てきているのではないでしょうか。
伊藤:学術分野では、国家的機微技術をどう守るかが問われます。われわれ大学が求められているのは、素粒子などの基礎物理や基礎数学など、交流を深めることのできる学術分野と、安全保障に基づく輸出規制対象となるような技術分野をしっかり分けて対処することだと思います。これを研究者の常識を基に判断することは避けるべきで、プロトコルを系統的に作り、それを基に判断する。「ここまではどの国・地域の学生であろうと、自由に一緒に思いっ切り研究してください。でもここからは機微技術に関わるから気を付けましょう」と。そのプロトコルをしっかり構築することにより、学術的、文化的な交流が保てるのではないか、というのがわれわれの期待です。
北山:学術的バックボーンや学んだ環境が同じ人だけで物事を考えるのではなく、バックボーンの異なる方々と一緒になって取り組むことは、イノベーションにおいては必須要件だと思います。自分たちとは異なる考え方を寄せ集めて、その中から突破口を見つけていく。その形がないとイノベーションは起こらないことは誰もが分かっているはずなのですが、そのように持っていこうとすると、いろいろな障害が次から次へと出てきます。先ほど先生がおっしゃった成功段階にまで行くために、私たちは何をしていけばいいのでしょうか。オープンイノベーションの下、新たなブレークスルーを起こすためにどのような人材を育成すべきでしょうか。
伊藤:量子コンピュータ研究は、現場レベルなら誰でもできます。例えば、アルゴリズムとソフトウエアに関する応用数学分野はそれほど成熟していませんので、数学の修士を取った人が初めて量子コンピュータに向き合ったとしても、半年もたてば最前線で研究を進めることができます。また、一つ一つの要素技術は半導体技術などとあまり変わらないですし、電気工学科、機械工学科、情報工学科、数学科、材料科学科などの出身者たちで、全てのパーツ、アルゴリズム、ソフトウエアはカバーできます。むしろ、量子コンピュータ研究で本当に必要とされる人材は、パッケージに関わるような全体のプランニングをする人、指揮官なのです。よく量子人材が不足しているといわれますが、それは「1台の車全てをデザインできる人がいない」といっているのと同じです。一つ一つのパーツや、やるべきことさえ決まれば、ナビゲーションも含め、全て今の技術で、科学技術を学んだ方々のそれぞれの特長を生かせばできるのです。要は、全体をまとめ上げられる人がいないということです。
北山:私は2022年の3月に日立製作所の役員を退任し、4月に日立総合計画研究所の会長に着任しました。当社のような調査研究を行う組織で必要となる能力は、全体をコーディネートする能力であり、その養成が課題です。また以前の立場から申せば、日立製作所でも同じくコーディネーターとしての役割を担うことができる人材の育成を重視しています。そのためには経験が必要ですが、全く失敗したことがない人がいいアウトプットを出せるかというと、必ずしもそうではないのです。致命的な失敗はまずいですが、小さな失敗を何度も繰り返すことで、プロジェクトを進める上での勘所が醸成されてきます。それは、自分の経験を生かそうと思える分野で初めて培われるものですし、それができる人はそれほど多くはありません。そのような人たちを育成するために、昔ながらの方法ですが、OJTの場で「失敗してもいいから」と実際の仕事をやらせてみる。そのやり方をメンターが見ていて、側面からサポートし、新たな考え方や取り入れるべき視点について助言する。いちばん重要なのは、ある程度任せてみて、「失敗してもいいから」といいながら場を与えることだと思うのです。そういう意味では、Q-STARは、「一度やってみたらどうか」という思いで立ち上げられたわけで、自由度がある中で試行錯誤することは、企業にとっても大きく伸びていける場なのだろうと考えています。
伊藤:私は幸いなことに、好きな研究をやっていいよといわれ、98年から自分でシリコン量子コンピュータの研究を始めましたが、その過程では、それはおかしいとか、そんなのは使い物にならない、などと学会で多くの指摘を受けました。当時はガリウムヒ素という化合物半導体による量子コンピュータが先行していましたから、シリコンは○○だからできない、といろいろな理由を突き付けられたのです。それらの指摘を乗り越えるため、数値も含めて徹底的に調べ上げ、物理的な結果を出していく必要がありました。ただ、これは基礎研究ですから、結果としてどのようなパッケージを作らなければならないかは、チップレベルでは分かっていても、システムレベルでそれができるかというと、私には判断できないわけです。量子コンピュータとシステムの人たちでチームをつくらなければいけないでしょう。Q-STARでそのような人材が育っていけば、その後は必ずしも量子コンピュータの知識がなくても、それぞれの分野の専門家に入ってもらって研究開発や社会実装を進めていくことが可能になると思います。
北山:量子コンピュータの社会実装は1社だけでは難しいわけですから、コンソーシアムの在り方が重要で、誰がどのように関わるかをうまく設計しないと成立しないのではないでしょうか。電機業界や自動車業界では、これまでそれぞれが築いてきた技術分野が確立されていますが、今後テクノロジーの在り方が変わってくることで、それぞれの業界を乗り越え、企業が取り組む技術開発の範囲を変えていかなければ乗り切れない時代が来るのではないかと感じています。今やもともと何の会社だったかというGoogleが良い例ではないでしょうか。
北山:最後に、日立と日立総研に向けて助言をいただけますでしょうか。
伊藤:日立の研究所といえば、われわれの分野では残念ながら亡くなられましたが、ノーベル賞候補だった外村さん*5がいらっしゃいました。他にも物理、化学、材料、全てにおいて世界でトップレベルの知見をお持ちの研究所であることは間違いありません。
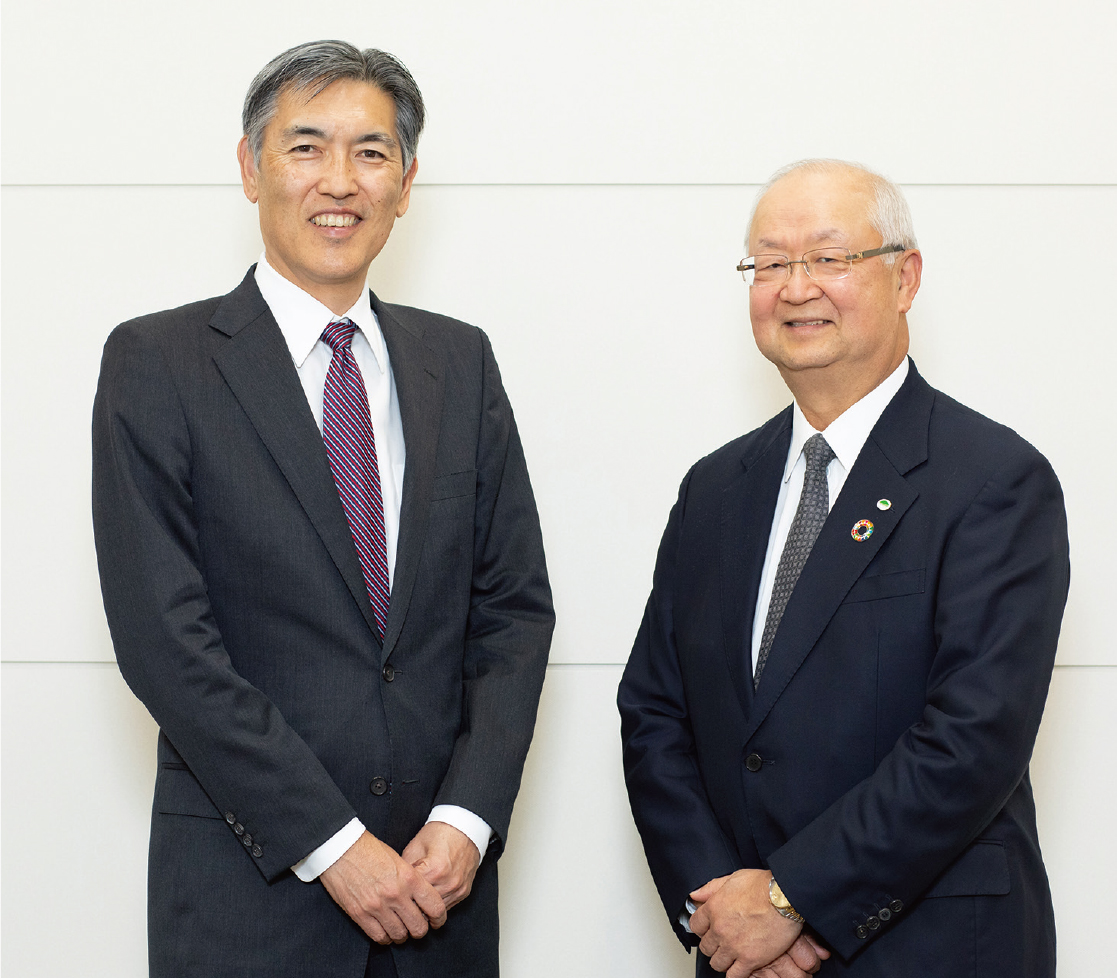
これはわれわれ大学の反省点でもありますが、足りない点を一つ挙げるとすれば、いろいろな人材を受け入れてこなかったこと、これに尽きると思います。慶應義塾大学には毎年約6,500人の新入生が入学しますが、もし100の国・地域から20人の新入生を受け入れれば2,000人、30人受け入れれば3,000人の多様なバックボーンを持つ人々が含まれることになります。そうなれば世界が全く変わります。100の国・地域に門戸を開けば、ある特定の国・地域に偏らないで済み、分断の問題も小さくなって、当事者同士にとって良い学びの場になるはずです。本来理想を語るべき大学が、このような理想を語ってこなかったことが、まずわれわれの反省です。特に少子化が進む日本においては、今後の経済発展を支える若者を増やさなければなりません。若者たちに、ただ日本に来てくださいというのではなく、一緒に学ぶ場所を作り、結果として彼らが日本企業に残るような教育を提供できれば理想だと思います。大学の反省点は、スタートラインに立つ若者たちに対して、そのような環境を今まで与えてなかったことだと思います。われわれがそのような学び場を作れば、ボトムアップで企業も変わっていくのかもしれません。いろいろな国・地域から、いろいろな考え方をする人が来た暁には、この製品をブラジルで売りたいのだったらこういう工夫をした方がいいとか、そんなネーミングではオマーンでは駄目だなど、私たちには考え付かない意見が出てきて、思いもよらなかったことが分かるようになってくるのではないか、というのが私の肌感覚としてあります。これまで日本がこれだけの高い技術を誇り、高い規律・規範を守ってきた中、後はそこにどこまで多様な考え方を取り入れられるようになるかがポイントだと思っています。
北山:多様性を取り入れる難しさをつくづく感じているところです。日立の役員には海外出身、例えば米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア出身の方が入っていて、これほど考え方が違うのかと思うことが日常的に起きていました。コミュニケーションの際にネックとなるのは、異なる言葉や文化への抵抗感です。抵抗感がなくなってくれば、相手に対して言いたいこともはっきり言えます。そういう本音の会話が進むことが、相互理解の始まりだと思うのです。そのためにも、先生がおっしゃるようにバックボーンの異なる人たちを集めて交流を促すことが必須だと思いました。本日は大変奥深いご意見をたくさんいただきました。本日はどうもありがとうございました。
※今回の対談は、フィジカルディスタンスを保って実施しました。
※Googleは、Google LLCの商標または登録商標です。
※IBMは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。
※本誌記載の会社名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

もはや量子コンピュータの知識がない人も開発に携われる段階にあるというお話は衝撃的でした。一時代前は夢のような話だった量子コンピュータが実用化の時代を迎えたことは、伊藤先生をはじめ多くの基礎研究者の努力のたまものであり、感謝したいと思います。関連する技術分野は多岐にわたり、今後は企業間や産学の壁を越えた協創がより一層必要とされるでしょう。その先の開発競争を生き抜くためにも、ダイバーシティを前提にした人材育成が急務であるとの意を強くしました。
株式会社日立総合計画研究所 取締役会長 北山 隆一