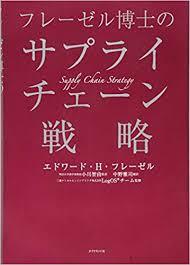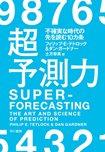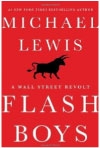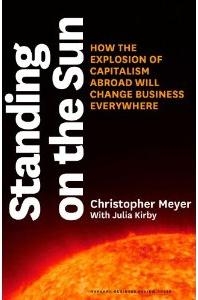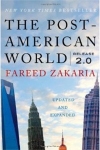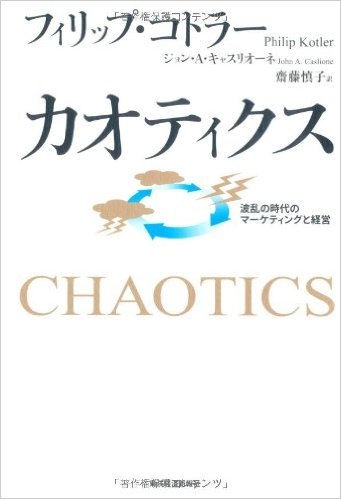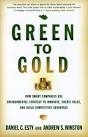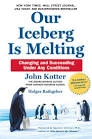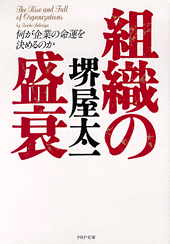研究員お勧めの書籍を独自の視点で紹介
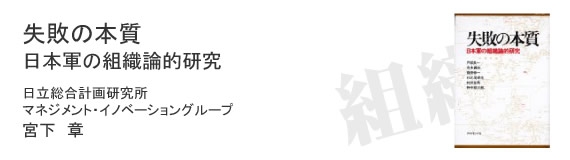
2006年3月22日
本書は1984年に、野中郁次郎、寺本義也といった日本を代表する組織論の研究者を含む6人で執筆され、20年を経た今でも古さを感じさせない、普遍性をもつ名著である。2005年、本書の続編にあたる『戦略の本質〜戦史に学ぶ逆転のリーダーシップ』が出版され、こちらもベストセラーに位置付けられたようであるが、20年を経て同じ執筆陣で続編が出ることからも、本書の名著ぶりを伺い知ることができよう。
本書は、第二次世界大戦における日本軍の敗北を組織論の切り口で分析したものである。すなわち、「組織としての日本軍は、米軍という組織に決定的に敗れた」と結論付け、この失敗の教訓を現代の企業経営に生かすことを究極の目的として執筆されている。世界大戦を題材とした壮大なケーススタディーと言ってもよい。
本書は3章から構成されている。1章では、ミッドウェー作戦、沖縄戦など6つの作戦における計画、実行面における問題点を個々に分析し、2章ではすべての作戦に共通する性格を抽出した上でその失敗要因を掘り下げている。3章では「失敗の教訓」と題し、「自己革新ができない組織は新たな環境に適応できない」として、自己革新能力創造の必要性を説いている。
おそらく、本書を読み終わった後に、多くの読者は「うちの会社も日本軍と共通点が多い!」と膝を打つのではないだろうか。本書では、日本軍と対峙した米軍が自己革新能力を備えていた、として対比されているが、最近、市場を席巻している競合他社がこの米軍と重なって見え、背筋を寒くしたのは、私だけではないだろう。
さて、著者によれば、日本軍の最大の失敗の本質は「特定の戦略原型に徹底的に適応しすぎて学習棄却ができず自己革新能力を失ってしまったこと」であるが、もう少し細かく3つに砕いて、日本軍という組織の失敗要因を見てみよう。
戦争の目的は戦争に勝つことである。議論の余地もないように見えるが、では何をもって「勝ち」とするのか、実は決めておかなければいけない。個々の作戦においても、ミッドウェー島の基地をつぶすことが目的か、迎撃してくる敵の機動艦隊を壊滅させることが目的だったのか不明確で、幹部間で意思統一がなされていなかった。
組織学の第一人者バーナードによれば、組織(チーム)の3要件は、(1)共通の目的、(2)貢献意欲、(3)コミュニケーションであるが、日本軍という組織には、(1)と(3)が不足していた。
帝国陸海軍は、それぞれ強力かつ一貫した「ものの見方(戦略原型)」に支配されていた。そして、その「ものの見方」が常に戦略的使命に影響を及ぼしていた。帝国陸軍が個々の作戦で共通に準拠していたのは、陸上戦闘において戦勝を獲得するカギは「白兵戦における最後の銃剣突撃にある」という「ものの見方」であった。この‘銃剣突撃主義’のルーツは、西南戦争に従軍した幹部が敵対した、旧薩摩藩士の示現流(相手に突撃して一刀で敵を倒すことを信条とする)であったとされる。一方の海軍の戦略原型は‘艦隊決戦主義’であり、このルーツは、日露戦争においてバルチック艦隊に完全勝利を遂げた日本海海戦であったとされる。
これらは「成功の復讐」と呼ばれる現象にも似ている。つまり、成功体験が強烈だったゆえに、それを基に戦略原型を固定してしまい、外部環境が大きく変わった時に適応できずに負けてしまうという現象である。経営学者クリステンセンの『イノベーションのジレンマ(The Innovator`s Dilemma)』にも、そのような事例が紹介されている。
日本軍の最大の過ちは「言葉を奪ったことである」。すなわち、時代とともに戦い方が変わり、第一次大戦以降、歩兵と艦隊から航空機と重火力が戦いの主役になっていても、戦略原型が破られることはなかった。これは、組織の末端の情報、アイデア、問題提起が中枢につながることを促進する「青年の議論」が許されなかったことと、そもそも情報を軽視していたことが大きく影響している。
私はこの本を読んだすぐ後に、映画『ラスト サムライ』を見た。‘サムライの遺伝子をもつ我々日本人へ’というキャッチコピーが広告のどこかに使われていたと記憶している。この映画にさらにインスパイアされた私は、日米軍の組織の違いの根底にある‘遺伝子’、すなわちサムライ文化と西洋流の哲学やキリスト教宗教文化の違いに、思いを巡らせた。つまり生身の人間である主君を絶対とするサムライ文化に対して、キリスト教においては、理想の姿を崩すことはない神が絶対の存在である。神の前で人間は小さい存在であり、懺悔などの儀式を通して、常に自己を見つめ直して悔い改める考え方が根底にある。西洋哲学のヘーゲル「弁証法」しかり、常に自分に向き合い見つめ直し、自分と異なる考え方に耳を傾け、そこから自分の考えの制約・限界を知った上で、自分の考え方を発展させていく。
無論、当時の米軍幹部の頭に、キリスト教や西洋哲学がどこまで浸透していたかは確信できないし、本書でも言及していない。しかしながら、本書の著者が薦める「自己革新組織」とは、哲学的な思考法の領域に踏み込んだ深遠なものなのではないかと、ため息が出る思いである。
著者の1人野中郁次郎氏は、この後「自己革新組織」に対する研究を掘り下げ、『アメリカ海兵隊〜非営利型組織の自己革新』を著し、1996年には経営学の名著と謳われる『知識創造企業』をまとめ上げる。いわば同氏はその研究人生を、日本軍をアンチテーゼとする理想的な組織の研究に捧げてきたとも言えるが、本書はそこに至る同氏の思考の軌跡が読みとれる一冊である。本書が刊行された1984年はおりしもプラザ合意の直前であり、その後日本はバブルに飲み込まれ失われた10年を経験する。いわば日本は、再び敗戦と戦後を迎えるのである。本書がバブルに歯止めをかける役割を担ったとは思えないが、その刊行のタイミングの良さには、改めて頭が下がってしまう。