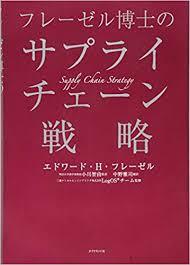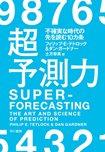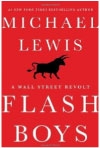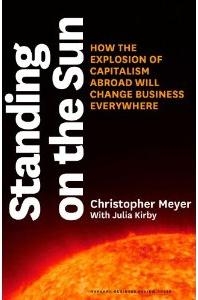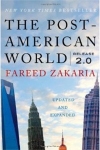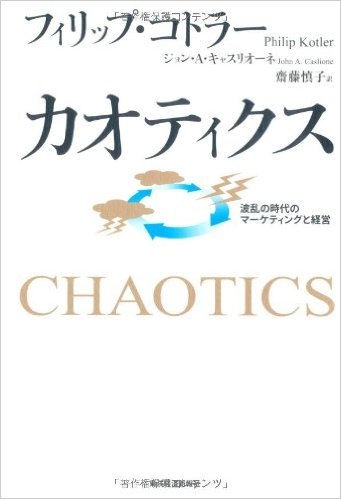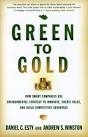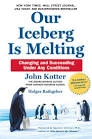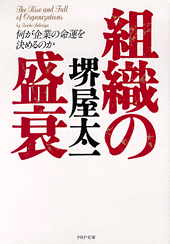研究員お勧めの書籍を独自の視点で紹介
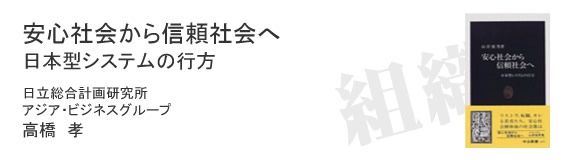
2006年7月24日
著者は「社会心理学」という研究領域の専門家であり、本書も基本的にはその領域に属する問題を扱っている。しかし、近年、企業の体質改善・風土改革のあり方などをめぐってこの研究領域への関心が高まり、「会社を変える」とか「強い組織をつくる」といった議論の中で本書が参照される機会が増えている。もはや定番となっている感もあるので、本書をご存知のビジネスマンは少なくないだろう。
本書の内容を強引に一言で要約するなら、「他人を信頼することが本人にとって有利な結果を生み出す社会的環境と、他人を信頼しないことが有利な結果を生み出す社会的環境が存在し、その環境はわれわれ自身が決めている」ということになる。このうち、「他人」のところを「上司」(または「部下」「同僚」)と、「社会的環境」のところを「会社」(または「職場」)と読み替えれば、本書の議論が企業組織のあり方を考える上で直接参考になることがうかがい知れよう。
著者のメッセージはパラドキシカルで、極めて刺激的である。例えば、日本企業は長らく社員間のチームワークの良さを最大の武器として、個人主義をベースとする欧米企業を猛追してきた。少なくとも一般的にはそう信じられてきたわけだが、著者の研究によれば、実は日本は昔から組織内の信頼関係が弱い(あるいは必要としない)社会である。つまり、日本企業の「和」というのは、相互監視システム的な伝統によって生み出された、能動的な意味で信頼関係を構築することを必要としない、みんなが同じ環境にいるという安心感から生まれた安定であり、必ずしもそこに強い信頼関係が存在することを意味しない。一方、さまざまな人種、文化、価値観から構成され、社会階層が絶えず激動してきた欧米(特にアメリカ)の社会は、相互の信頼関係をゼロから構築するという苦難の試みを長年続けており、この点では日本よりも伝統があるということになる。
このような論点を整理するために、著者は、日本社会が伝統的に持っている安定性を「安心」と呼び、独立した個々人が相互に尊重し合う関係を「信頼」と呼んで、両者を区別している。
もちろん、著者の主張には、これまでに国内外の多数の研究者(著者自身も含む)が行ったアンケート調査や心理学的な実験(友人関係にない他人同士が協力して作業するときの傾向調査など)の裏付けがある。ちなみに上記の例は、日米で行われた信頼度の比較実験から導かれたものであるが、本書には、これ以外にも多くの興味深い研究結果が記述されている。いくつか象徴的なもの挙げるとすれば、以下のとおりである。
現在、日本では終身雇用制度の崩壊や犯罪件数の増加など、社会や組織の安全が脅かされている。しかし、本書の脈絡から言えば、それは「信頼」の崩壊ではなく、あくまでも従来の日本型の「安心」の崩壊ということになる。そして本書は、これからの日本社会は関係内部での相互協力と安心だけでは得られない新たな機会に直面するとした上で、従来型の安心システムから、新たな信頼システムへと移行できるかどうかが、社会や経済の効率的な運営にとって重要になると論じている。
本書に対しては、「偏差値が高い学生のほうが他人を信頼する度合いが高い」などといった、差別的な意味での誤解を与えかねない実験結果や、単純な心理実験の結果を安易に社会全体の結論に拡張しているなどといった点に関して、ある種の批判が存在するようである。しかしながら、知識社会の到来が叫ばれ、情報通信技術の爆発的な発達によって意思決定の方法や情報伝達の手段が急速に変化し、新たなコミュニケーションとチームワークが必要になっている現在の組織環境を考えると、著者が提唱する「安心社会から信頼社会へ」の発想には、十分傾聴に値するものがある。