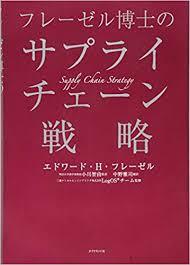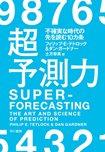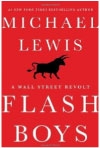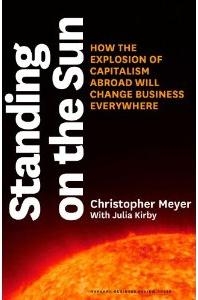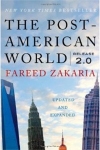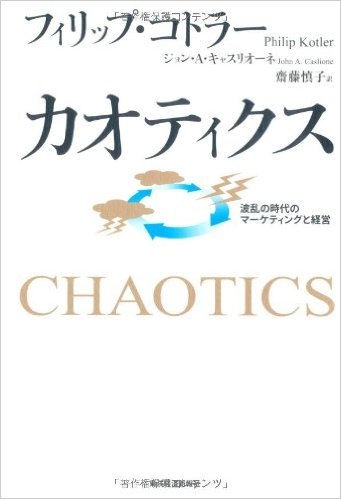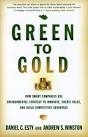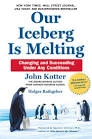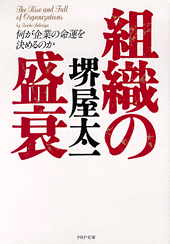研究員お勧めの書籍を独自の視点で紹介
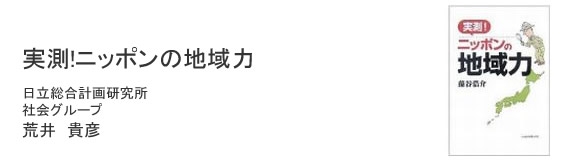
2009年4月22日
著者の藻谷浩介氏は、日本政策投資銀行で長年にわたり地域経済の調査研究に携わっており、「平成合併」前の全市町村(約3,200)の99%を訪れて得た知見を生かし、内閣官房が認定する地域活性化伝道師としても活動している。「中心市街地活性化のポイント」(ぎょうせい2001年)の編著などに携わるほか、年間約400回の講演を通し地域の活性化を支援している。
本書では、タイトルに「実測」とある通り、統計データを用いて地域の現状や将来性が読み解かれているが、地域の実情を踏まえた著者独自の分析方法により非常に興味深い内容となっている。「まず常識を疑ってみよう」というのが本書の隠れたテーマであり、目次だけ見ても、「でも……日本の子供の数は減っていない」「首都圏で破綻必至の医療福祉体制」「『大都市ほど成長』は誤解」「交通網整備は地域活性化に直結しない」など、これまでの常識と相いれない項目が列挙されている。
多くの方が自身の認識との相違に驚きを覚えることと推測するが、これらは視野を変えれば見えてくる常識の裏に隠された一つの真実なのである。
一例として、日本の子供の数について紹介しよう。少子化を示す指標としては、一人の女性が一生の間に産む子供の数に相当する期間合計特殊出生率が一般的に使われている。そして、その推移を見てみると、団塊ジュニア世代が生まれた1970年代前半までは2を超えていたものの、1980年に1.75、1990年に1.54、2000年に1.36、2005年に1.26となっており、確かに出生率は急速に低下している。
では、実際に生まれた子供の数はどうであろうか。1990年は1980年と比較して23%(約36万人)減少したのに対し、2000年は1990年比2%(3万人)減と、出生率の低下ほど子供の数が減っていないという事実が浮かび上がるのである。
その要因を読み解くには、まず期間合計特殊出生率の算出方法を見る必要がある。期間合計特殊出生率は、その年における15歳から49歳までの女性の年齢別出生率(n歳の女性が産んだ子供の数÷n歳の女性人口)を単純合計した数値であり、どの年齢の女性人口も同数として算定されている。一方で、日本の年齢別人口構成図(人口ピラミッド)は、団塊世代と団塊ジュニア世代の二つのふくらみを持つ「逆ひょうたん型」となっている。結果として、団塊ジュニア世代が20代を迎え親に成り始めた1990年代には、親世代(年齢別出生率が高い20代から30代前半までの世代)の人口が増えたため、出生率の低下ほど子供の数は減らなかったのである。
なお、今後は団塊ジュニア世代が出産のピークを越え親世代の人数も減少するため、出生数の減少が加速すると予測されている。著者は、現在の出生数を維持するだけでも、出生率を2.1程度まで引き上げなければならないと分析している。
また、地域間格差、地方都市の衰退という言葉も、近年よく耳にする言葉である。これらは、経済成長の基盤である人口が流入し大都市が形成されたことを根拠にするものである。しかし、過去の成長の結果である現在の都市の人口規模と、今後の成長の可能性は必ずしも一致しないのが実態であり、著者は、大都市であれば成長し地方都市は衰退するという二分法は成立しないと分析している。もちろん、多くの地方都市では人口が減少しているが、産業振興策などで人口を増加させている都市も少なからずある。また、大阪府のように人口が流出している大都市もある。それにもかかわらず、大都市東京のイメージがあまりにも強いため、大都市は成長するという固定観念が形成されていることに懸念を示している。その上で、首都圏など大都市の問題として、高度経済成長期に流入した団塊世代の高齢化と若年人口の減少による医療福祉体制崩壊の危険性が提示されている。
ここで紹介したものは本書の一部に過ぎないが、これだけでもデータの見方や切り口を変え、多面的にものごとをとらえることの重要性を理解できる。
サブプライムローン問題に端を発した世界同時不況が日本の実体経済にも影響を及ぼしている昨今、日本は、この影響を最小限に抑え早期の回復を図るとともに、グローバル社会が抱える地球温暖化、資源の偏在、高齢化などといった非常に難解な課題にも取り組む必要がある。しかし、これらの課題は、今までの常識を踏襲するだけでは解決の糸口を見いだすことが困難である。本書が提唱する常識に疑問を持ちさまざまな角度からデータを検証する姿勢こそが、今求められている。
本書は、まちづくりに携わる人向けの書籍だと思われるかもしれないが、データの分析手法や変化のとらえ方など、読む人に何かしら新しい気づきを与える良書である。多くの方に読んでもらいたい一冊である。