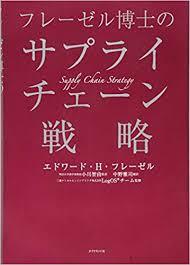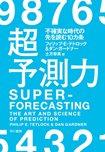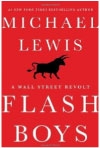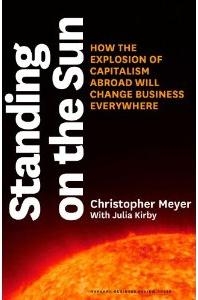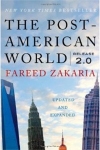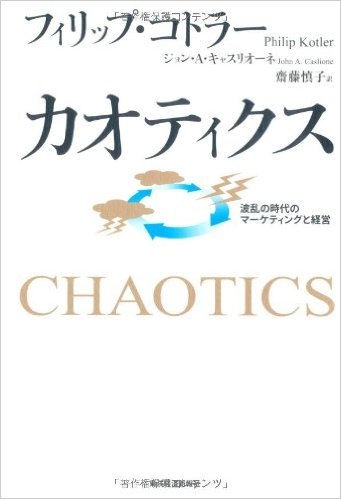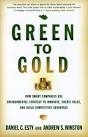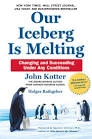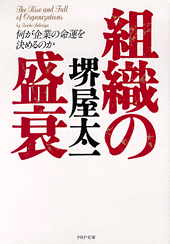研究員お勧めの書籍を独自の視点で紹介

2009年1月11日
目下世界は、サブプライムローン問題に端を発した歴史的な金融危機に見舞われている。欧米の金融機関が隆盛を謳歌(おうか)してきた裏に、リスク管理の甘さがあったのではとの指摘が、今になってなされている。しかし、単純にそうなのであろうか? 評者はかつて財務の一担当者として、複数の事業の業績を束ねて管理していた経験があり、各事業の長期計画・予算計画に、どのようなリスクが含まれているか、しばしば幹部の下問を受けた。各事業のマネージャはそれぞれが、非常にさまざまな事象をリスクと認識しており、画一的な評価が困難で思うように整理・数値化できなかった苦い経験がある。そもそも、リスクとは何であろうか?把握することも困難なリスクを完全な管理下に置けるのであろうか?本書のサブタイトルにある、「神々への反逆」という言葉にひかれ、評者の疑問への解が含まれているのではとの期待を胸に本書を手にした。
著者であるバーンスタイン*1は、長年に亘るニューヨーク連銀や投資顧問会社経営の経験を踏まえ、現在と過去と一線を画す画期的なアイデアとしてリスクの考え方を挙げている。斬新な切り口である。リスクの語源は「勇気を持って試みる」ことで、元来受動的な意味はなく、能動的に未来を選択する意味を持つのだという。「神々への反逆」とは、古の人にとって、神の手のひらの中にあると思われた未来を、近代西洋の人々が、確率論を武器に人間の手に手繰り寄せてきたさまを指している。確率論をもとにしたリスクの考え方が発見される以前は、「未来は占い師が闊歩(かっぽ)する領域」であった。
年代記風に語られる数々のリスク発見のエピソードはリスク概念の形成史となっており、大変興味深い。リスク概念の誕生は、15世紀後半、簿記で有名なイタリアの修道士ルカ・パチョーリが「賭博を途中終了した場合の掛け金の分配方法」を例にした数学クイズを簿記の本に提示したことにさかのぼる。約200年後フランスの数学者パスカルが確率論を元に問題を解いたことでその具体的な定量的分析の研究が始まった。ルネサンスの3大発明は、火薬、羅針盤、活版印刷といわれるが、著者は、簿記と、リスク予測能力であると断言する。「2つの活動なくして資本主義は発展し得なかった。一つは簿記であり、ささいに見えても、この活動のお陰で数を記録したり、計算をしたりする新たな技術が普及していった。もう一つは予測である。(中略)成功した経営者はまず第一に優れた予測者である。仕入れ、製造、販売、値付け、組織作りなどは、全て後の問題である」とのこと。評者も同感である。
リスク概念や確率論の発達は、やがて、コンピュータの大量計算に基づく現代的なリスク・マネジメントに行き着く。「経済や金融の変数の多くが釣鐘型曲線に近い分布になるとはいえ、その図形は決して完璧な釣鐘型ではない。真実に似ていることと真実は同じではない。野生はこういった異常値や不完全さの中に潜んでいる。」と、コンピュータに依存しきった意思決定に警笛を鳴らしている。今日の金融危機の惨状も予見しているようで正に至言である。それは、コンピュータの出す結果を半ば「神のお告げ」として盲目的に受け入れているに過ぎず、誤った行為であるという指摘にもとれる。「われわれの決定的に重要な局面において、神は人類に確率の薄明かりのみを与えてくださった。けだし、この薄明かりさえあれば、神が我らに与えた凡庸さと神に召されるまでの期間には十分だからである」と慎ましい言葉で、著者は本書を結んでいる。
未だに損失の全体像がわからないサブプライムローン問題を発端とした金融危機をみても、証券化によるリスク分散効果に関し、内在するリスクの軽視や、金融技術への過信があったといわれる。しかるに、2011年をめどに急ピッチで統合が進んでいる国際会計基準は、リスク・リターンの関係が非常に重視されているといわれ、必然的に、ERM(統合的リスク管理)など、リスクの把握、計量化、回避方法について統合的に管理するニーズが高くなるものとされている。しかしながら、そのようなERM等導入の前提として、そもそもリスクとは何であるか、また、どうやってリスクに立ち向かうべきなのかなど、リスク統制に携わる人々のもつリスク概念を整理する必要があるというのが評者の結論。多くの人に本書を読んで戴きたい。