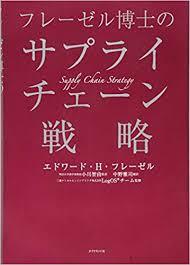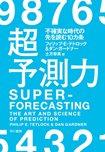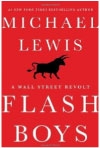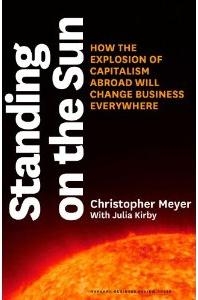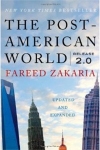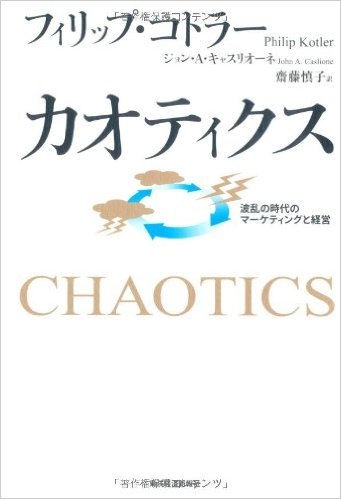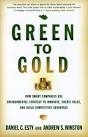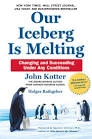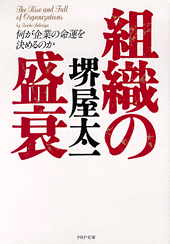研究員お勧めの書籍を独自の視点で紹介
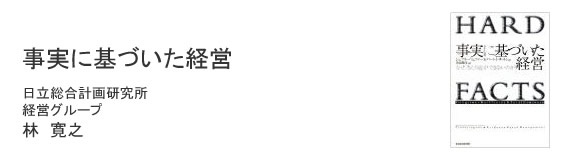
2011年3月30日
本書の原題は、“Hard Facts, Dangerous Half-Truths, and Total Nonsense: Profiting from Evidence-Based Management”である。世間に広く流布している経営手法や常識が事実の裏付けのない“Total Nonsense”であったり、特定の会社の特定の時期にのみ適合するが、ほかには合わない“Half-Truths”であったりすることを指摘し、戦略の意思決定が本当に自社の現況に適したものであるかを検証し、“Hard Facts”に基づいた経営をせよと説く書である。
本書の著者であるスタンフォード大学ジェフリー・フェファーとロバート・I・サットン両教授が、「事実に基づいた経営」(Evidence-Based Management)が必要と考える元になったアイデアは、医療界における「根拠に基づく医療」(Evidence-Based Medicine)の考え方である。医師が学生時代に習ったとか、その病院やその地方の昔からのやり方だとか、その分野で権威がある医師のやり方だというだけでは、根拠に基づかない医療行為が存続してしまう。そのため、治療法を二重盲検法(ダブル・ブラインド・テスト)で検証し、その中で蓄積された事実から根拠に基づかない医療を振るい落としていく。これが、根拠に基づく医療である。二重盲検法とは、患者だけでなく、医師にも、真薬か偽薬(プラシーボ)か知らせずに試薬を与え、真薬を与えたグループと偽薬を与えたグループ(対比グループ)との間で効果に差が生じたかを検証する方法である。患者が効くと思って薬を摂取すると、たとえ偽薬であっても自己暗示で実際に効いてしまうプラシーボ効果を排除するためである。しかし、経営の世界で実験を行うと、関係者は医薬の世界のようにブラインドな状態ではありえない。各自が何らかの情報を持っており、どのような反応・結果を期待されているかも分かってしまうからだ。従って、経営の世界では、厳密な意味での二重盲検法を行うには無理がある。それでも、データの収集、調査・分析、現場での実験が事実に基づいた経営につながると著者は説く。現場で実験することが大切である例としてセブン‐イレブンの親会社であるサウスランド(当時。現在の親会社はセブン&アイ・ホールディングス)の事例を挙げている。顧客に近づき、サービスをとことん追求する同社では、顧客に対して目と目を合わせ微笑みながら感謝を示す運動を広めていた。店員が礼儀正しさを競い合うコンテストまで開催していた同社だが、複数の店舗で実験をしてみると、店員の礼儀正しさと売上との間には何の関係もないことが証明された。顧客が求めていた良いサービスとは、早く買い物が済ませられることであって、見せかけの微笑ではなかったのだ。
本書では、有名な企業に関するいくつものケーススタディを取り上げ、その企業の事実に基づかない判断・行動を指摘している。評者が興味深く読んだケースが、ユナイテッド航空によるサウスウエスト航空のベンチマークである。このケースは、何が真実なのかを探求せず、著者が批判する「目立ち、わかりやすく、それほど重要ではないところだけを真似する」ベンチマークが、いかに企業経営を誤らせるかを教えてくれる。効率経営で高い業績を上げていたサウスウエスト航空に対抗しようと、ユナイテッド航空は「シャトル・バイ・ユナイテッド」というローコストキャリア(LCC)を立ち上げた。ゲートのスタッフやフライトアテンダントの制服をカジュアルなものにし、機体はボーイング737だけを使い、ユナイテッドとは別の乗務員を使い、機内食を出すのを止め、地上での待機時間を減らして航空機の回転率を上げた。これらはすべてサウスウエスト航空の成功要因として広く信じられていたことである。しかし、現実にはサウスウエスト航空のシェアが増え、シャトル・バイ・ユナイテッドは失敗に終わった。著者は、サウスウエスト航空の成功要因は企業文化と従業員を大切にする経営方針にあるとし、ユナイテッド航空は航空機の回転率を上げるといった表面的な分かりやすい取り組みを真似しただけで事実に基づいた経営になっていなかったと分析する。
自分が信じていることやよくいわれるやり方にはウソが半分含まれていることが多く、そうしたHalf Truthsにこだわり過ぎることは危険だと説く。そうしたHalf Truthsの一例として、「戦略がすべて」という考えを挙げている。「戦略がすべて」と思い込むと、業績が良くないと、戦略に問題があり見直すべきだと考えがちになる。しかし、問題は戦略ではなく実行にあることもある。著者がコンサルティングをした、ある医療画像機器メーカは、アメリカ市場での売上が伸びない問題にあたり、商品戦略や価格戦略が間違っているのではないかと悩んでいた。著者は、調査から戦略に問題があるのではなく、戦略が適切に実行されていない事実を明らかにし、営業部門のトップと担当者を交代させる提案をし、同社はこの提案を実施した。すると、アメリカでの売上はたった1年で2%成長から20%成長へと劇的に改善した。真の問題は商品や価格の戦略ではなく、営業がきちんと売っていなかったという実行の問題だったのだ。
「企業変革は難しく、時間をかけるべきだ」という考えも危険なHalf Truthsの一つとしている。企業変革そのものは確かに難しい。しかし、だから時間をかけるべきだと信じると、3つの効果が働く結果、企業変革は一層困難になると説く。第一、「締切効果」により、長い時間の先に設定された締切まで何もしなくなる。学生が提出締切直前まで宿題に手をつけないのと同じだ。第二、「緊急性効果」により、後回しにしても良いのだという悪いメッセージを関係者に与えてしまう。企業変革には時間をかけるべきという考えが、緊急性が低く大切なことではないという誤解を関係者に与えてしまうというのだ。第三、「難しいと思い込む効果」により、リスクを取ることはしたくないという人間の感情が先に立ち、前に進めなくなってしまう。
「偉大なリーダーは組織を完全に掌握している」という考えもHalf Truthsであり、そう信じることですべてをリーダーのおかげにしてしまい、ほかの要因に目が行かなくなる危険があると説く。著者は、リーダーが業績に対して大きな影響力を持っていることは否定しないが、リーダーを美化し、カリスマ的に扱うのは行き過ぎだと警告する。物事の白黒をつけたいという人間の性質からつい結果を過度にリーダー個人のせいにしてしまうが、原因と結果をきちんと見極めるべきだと説く。業績には、リーダーシップだけでなく、さまざまな要因が影響している。従って、リーダーシップの良し悪しに囚われず、何が本当に業績に大きく影響したのかを深く分析することが重要だとする。GEのジャック・ウエルチによる企業変革の成功要因を彼のリーダーシップのみに求めず、彼に協力した7万人以上の従業員の努力にも目を向けるべきだという。
著者は一見正しく見える経営手法を鵜呑みにせず、真に重要な要因が何であるかを追及することが正しい経営判断には不可欠だと説く。あらゆる経営手法にはプラスとマイナスの両面がある。データの収集、調査・分析、現場での実験などから事実を見つけ、それに基づいて行動することが事実に基づいた経営である。ある組織が事実に基づいた経営を行っているか手っ取り早く判断するためには、「失敗した人はどうなるか?」と尋ねるのが有効だと説く。医薬の世界でいう「許せ、しかし記憶せよ(forgive and remember)」ができていれば、いつ、どこで、なぜ失敗したのかを多面的に深く分析でき、経営を改善し、事実に基づいた経営に近づくことができる。事実に基づいた経営を実践し、そこから効果を得るには、自分が見逃していたこと、バイアス、問題を認め、それを解決するデータや理論を見つけることが必要であり、しかもそれはすべての問題を魔法のように解決してしまう一度きりの解決策ではないとする。だからこそ、こうした活動を毎日の中で実践することを強く勧めている。ピーター・ドラッカーの言葉を引用し、「考えることは大変な仕事だ。流行を取り入れれば、考えなくても済む」と、経営者に警鐘を鳴らす。流行の経営手法や従来からの常識に流されることなく、もう一段深く事実を求める姿勢を本書から学ぶことができる。