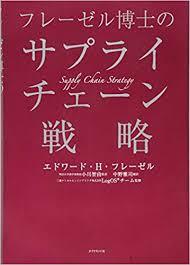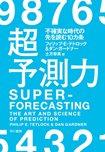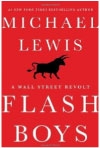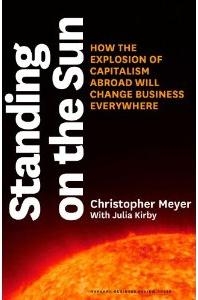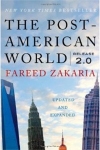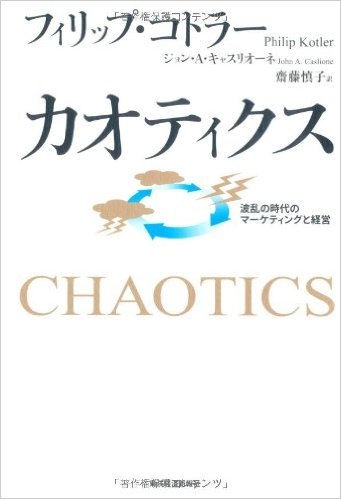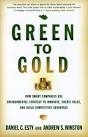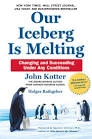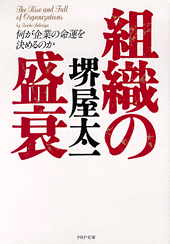研究員お勧めの書籍を独自の視点で紹介
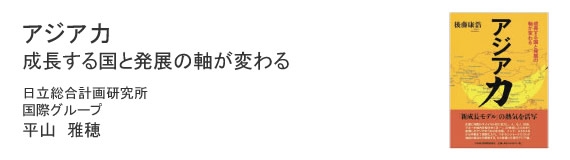
2011年4月11日
欧米経済は、金融危機で受けた打撃からの回復に時間を要している。一方、著者が「肥沃な三日月地帯」と表現する、中国から中東地域に至るアジア全域は、経済成長の熱気に包まれている。そのアジアの成長の原動力となっているものは何か。そして今、欧米と同じく不況から抜け出せずにいる日本がなすべきことは何か。著者である後藤康浩氏は日本経済新聞社中国総局(北京)の駐在経験があり、本書ではその著者の経験と、独自の視点から分析したデータをもとに、アジアの将来像と日本企業の進むべき道のヒントを記している。
本書において著者は「アジア力」とは「変化する力」であると述べている。ここ十数年、アジア経済のけん引役となってきたのは中国である。中国は、低賃金かつ豊富な労働力を武器とした労働集約型産業がけん引し「世界の工場」の地位を確立した。しかし、一人っ子政策による生産年齢人口の減少、低賃金労働者の賃上げ要求の影響で、労働集約型産業がけん引する産業構造は転換期を迎えている。一方、製造業で生み出された雇用で所得が増えた中流層の消費活動が活性化し、中国国内の需要が拡大している。中国は輸出主導の経済成長モデルから、内需主導の経済成長モデルへと産業構造の転換を進めつつある。中国に替わり、生産拠点として注目を集めているのがベトナムやインド、バングラデシュなどである。アジアの各国経済が新たな局面に移行し、成長・発展の中心となる国がそれぞれ変わっていくことで、生産と消費の増加スパイラルを生み出しアジア経済が底上げされていく。
日本は高度成長期において、アジアを「生産拠点」としてとらえており、そこでの生産物は主に欧米や日本国内において消費されていた。しかし、今後アジア中流層の消費欲求は膨張し、また、アジアに約20億人いるといわれる低所得者層の購買力も底上げされアジア全体の内需が拡大する。低迷する日本経済の回復は、拡大するアジア内需を取り込めるかにかかっている。ではそのアジア内需をいかにして取り込んでいくか。著者は、日本企業はより「現地に溶け込む」べきだと考えている。著者のいう「現地に溶け込む」とは(1)現地の生活者目線でのマーケティングと商品開発、(2)優秀なアジア人材の積極的採用(低賃金労働者としてではなく)、(3)日本人若手人材の現地投入、の三点である。(1)の例として本書では、シャンプーや蚊取り線香の小口包装販売が挙げられている。日本では「お徳用パック」(=たくさん入って小口で購入するよりも単価が下がる)がおなじみであるが、低所得者層においては、手元に資金があるときに少しだけ買える小口包装にニーズがあるのだという。(2)については、日本企業はアジアの人材を「低賃金労働者」としてみる傾向が根強く残っている。しかし、少子高齢化により労働人口が減少していく日本は、国境を越えて優秀な人材を取り込んでいく必要がある。また(3)は、入社1〜3年の若手を現地に期間の定めなく投入し、現地に即したマーケティング、製品開発《(1)》を実践できる人材を育てるべきだ、ということである。
著者の主張はもっともなことではあるが、恐らくは「わかっちゃいるけどそう簡単には踏み出せない」、というのが日本企業の現状ではないだろうか。しかし、決断を先延ばしすればするほど、日本の進む道は細く、険しくなるであろう。
本書はアジア各国の成長要因や今後の課題、アジアに内包するリスクなどを多角的視点で分析、推察しており示唆に富む内容である。アジアビジネスに携わる方だけでなく多くの方に読んでいただきたい一冊である。