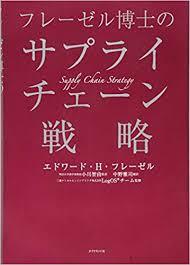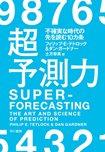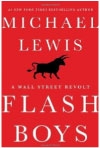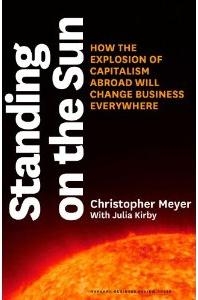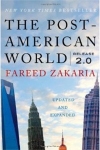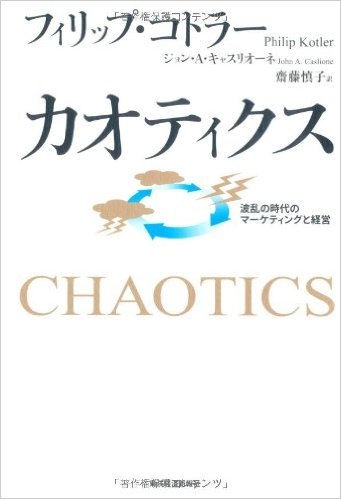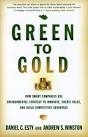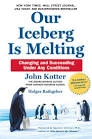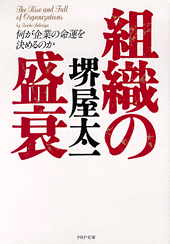研究員お勧めの書籍を独自の視点で紹介
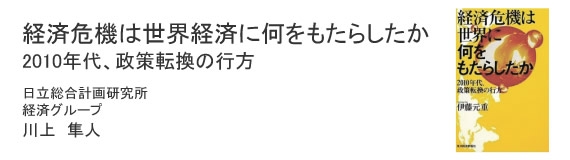
2010年2月9日
著者の伊藤元重氏は、エコノミストとして、学会だけでなく小渕内閣時の経済戦略会議にも参画するなど、日本の政策決定の場でも影響力を発揮してきた。テレビ出演や新聞への寄稿などで、一般的な知名度も高い。また、経済に詳しくない人でも読みやすく書かれた一般向けの著作も多い。本書でも、経済学の難解な領域にまでは踏み込むことなく、金融危機の構造分析をはじめ、危機後の日本経済、世界経済が抱える課題やチャンスが分かりやすく述べられている。
日本経済については、将来的に貿易収支が赤字に転落する可能性を、少子高齢化に伴う貯蓄率の低下や所得収支の黒字拡大などの要因から示している。また、為替レートを見る際は、円ドルのように一通貨だけに対するレートではなく、多通貨に対する平均的な実効レートを、名目ではなく物価の動きを加味した実質レートを、つまりは実質実効為替レートを見ろという。その上で、為替変動リスクと運命を共にする輸出依存の産業構造が持つ危険性を挙げている。いずれについても、例示や解説を混ぜつつ論理が展開されており、問題となる経済構造についても理解が及ぶようにまとめられていることが好印象である。
世界経済に関しては、中国の台頭や米国の相対的地位低下、東アジア共同体構想などについて述べており、その各所で日本経済の課題やチャンスに触れている。
中国は、金融危機による不況からいち早く回復を遂げ、世界の注目を浴びることになった。中間所得者層の飛躍的な増加が目立ち、質の高い日本の消費財も大きな可能性を持つと見られている。しかし著者は、欧米多国籍企業と競うためには、経営統合などによる企業規模拡大やブランド力強化の必要があると指摘する。また、中国企業との競争も激化していることにも言及している。これらは特別に斬新な視点という訳ではないが、企業経営者との接点も多い著者が現地での体感を基に考察しているため、説得力を持って響く。
一方米国に関しては、金融危機によって消費が減退し、世界経済のけん引役としての地位は新興国に移ったとする見方が多い中、著者は、米国経済の地位は相対的に低下するとしながらも、依然としてその規模は世界最大であり、なおかつ潜在力を持つことを強調する立場をとる。ここでいう潜在力とは、投資資金の受け皿としての経済規模、高い競争力を持つIT産業の存在、そして移民の増加によって今なお増加を続ける人口と市場のことである。特に、世界中から優秀な能力を持つ移民が集まること、移民による住宅や自動車の需要が増加していくことなど、米国が「新興国」としての側面を持つという表現が興味深い。これは、人口の移出入が極めて少なく、固定化された永住者の高齢化が進む日本のような国との対比として、特に重要であると思われる。
中国や韓国を含む東アジア諸国と日本の関係については、アジアの成長がこのまま続くことを前提に、経済的な協力関係を強めることの重要性を述べている。物理的な距離や人口の規模、域内分業に適しているというアジアにおける協力体制の利点を挙げ、ASEANをハブとしたFTAのネットワークを広げていくことや、東アジア共同体の構想についても言及している。そして、その構想の柱として、為替安定や金融安定の論議が盛んになっていることを示し、その中で通貨統合について考察している。通貨統合へのアプローチについては、ACU(アジア通貨単位)というアジア各国の通貨を合わせた合成通貨単位の創出と活用や、AMF(アジア通貨基金)のような機関を設立し為替介入のための資金をプールしつつ各国が政策の論議と調整を行えるようにする案を挙げ、マクロ経済の安定を実現させるステップとして紹介する。一方で、ユーロのような共通通貨の導入は、現実的ではないとする。共通通貨については、欧州における通貨統合の功罪を考察する中で、各国が金融政策の自主性を失うこと、域内における成長ステージ格差の調整が難しいこと、不況やインフレが波及しやすいこと、などのデメリットを挙げており、「共同体」というととかく共通通貨のイメージが浮かびがちな一般論に対し、専門家の立場から分かりやすい解説を加えている。
金融危機による世界経済の後退は、著者も「100年に1度」であると認めている。しかし同時に、「経済が暗い状況下の方が、それぞれの国、地域が抱える明るい面もよく見える」とも述べている。本書は、危機の発生によって浮き彫りになった諸問題や好材料を基に、危機後の経済を広範に見通したものであり、特にそれらを網羅的に、初学者にも分かりやすく伝えているという点に価値がある。社会人になって間もない方や、技術職から企画部門に異動した方など、リーマンショック後の世界経済をオーソドックスな視点で概観しておきたいというニーズを持つ方に、本書を薦めたい。